特別展「三国志」 “虚構”だった武勇伝がリアリティーをもって迫ってきた

「君は三国志の武将でいうと、簡雍(かんよう)だな。上司の前でも態度がでかい」。
会社員時代、同僚にそんなことを言われたなぁと、東京国立博物館(台東区)での特別展「三国志」の会場で思い出しました。
『三国志』は、西暦200年ごろ、いまの中国大陸で3つの勢力が争った「三国時代」を描いた歴史書などをいいます。特に歴史書としての『三国志(正史)』と、物語要素の強い『三国志演義』の2つがよく知られています。小説やマンガ、TVゲーム化される三国志は、おもに後者です。
開催前日の7月8日、報道陣向けの内覧会が開かれるというので、ひとりでカメラを持って参加してきました。この特別展では、個人利用目的であれば、一般入場者でも展示物の撮影ができます。

ちなみに前述の「簡雍」は、3つの勢力のひとつ、蜀(しょく)の将です。他の武将たちと異なり、合戦で活躍したとか、軍師として兵を導いたといった輝かしい記録は残っていません。にも関わらず、リーダー・劉備(りゅうび)の前でも物怖じせず、大きな態度をとっていたようです。その簡雍に例えられたのですから、当時の筆者の働きぶりがわかろうというものです。
報道陣向けの内覧会には、約230人が参加しました。老若男女、さまざまな世代の参加者がおり、三国志のファン層が幅広いことをうかがわせます。
入場前、音声ガイドの機械を借りました。三国志ファンの歌手・吉川晃司さんと、ゲーム『真・三國無双』シリーズの声優さんがナビゲートするものの2バージョンがあるとのことです。筆者が借りたのは吉川さんバージョンでした。
会場に足を踏み入れた筆者の目に飛び込んできたのは、フィクションからリアリティーへと移ろっていく三国志の世界でした。入口近くには、マンガ『三国志』(横山光輝/潮出版社)の一場面、「桃園の誓い」の原画がありました。

まさに物語としての三国志を象徴する1枚です。ここから三国志という名の「沼」にハマっていった人は多いでしょう。
展示はそこから三国時代のずっと後、清の時代に描かれた鮮やかな壁画を経て、これも後世作られた武将・関羽(かんう)の巨大な像へとつながります。
この像は、現在のヒゲの毛量が多く、体格のよい「武神」関羽のイメージができあがる前に作られたもので、身体が細くすっきりしていることが特徴であると、同博物館東洋室主任研究員の市元塁さんは教えてくれました。
歩みを進めていくと、三国志の中心人物である3人、曹操(そうそう)、劉備、孫権(そんけん)が確かにいたことをうかがわせるレンガや剣、玉(ぎょく)の展示があり、悪役のひとり董卓(とうたく)に関連する人物のものと考えられる副葬品や、張角(ちょうかく)にまつわる碑文がならび、次第にリアルな三国志が押し寄せてきます。

三国志を扱うマンガやゲームに触れながら、どこかで別世界でのできごとのように感じていた筆者でしたが、いま生きているこの時代から、劉備や曹操、孫権が大陸を駆けた時代につながっていることを確信していきました。
その思いをさらに強めたのが、2009年に発見された曹操の墓・曹操公陵の副葬品です。曹操が「情勢が不安定なので、派手な埋葬をしなくてよい」と遺言したとされる通り、見た目は実に質素なものでした。
また、孫権らが治めた地域で見つかったという棺を支える石は、孫家のトレードマークと呼ぶべき「虎」の形をしており、ここでも物語としての三国志が、リアルの世界へと直線的につながった感がありました。

「とはいっても、大部分はフィクションでしょ」。頭のどこかでそんな思いがあった三国志が、この特別展「三国志」を経て、急に「すぐ近くにあったもの」へと自分のなかでパラダイムシフトが起きた感覚を味わうことができました。

帰りに特別展「三国志」オリジナルの「ガシャポン」を回してみたら、マンガ『三国志』の猛将・呂布が、能書きはいらない、ただ楽しめばいいと言わんばかりに、「だまれ!」とこちらをにらんでいました。
この記事をシェアする
「ひとり体験」の記事

クリスマスはひとりで魚とすごそう! イブに楽しむ「おひとりさま水族館」
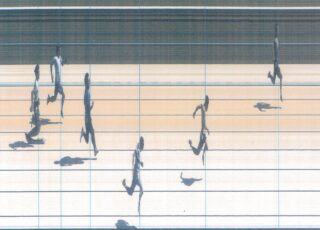
43歳のおっさん、100mを全力で走る!写真判定機で測ってみた!

閉園する「としまえん」 ひとりで遊びにいったら、いつのまにかビールで1杯やっていた

45歳の男が韓国・大邱で最新の顔美容を受けてみたら……

世界に一つだけの「陶片ピアス」〝おみみあい〟でマッチング 佐賀県が企画

「DANROひとり旅倶楽部」 東松寛文さんを迎えてイベントを開催!

「DANROひとり美食倶楽部」 宮城の魚とワインを味わうイベントを開催!

“ひとり飯”好きが集う「DANRO ひとり美食倶楽部」初イベントを開催!

幻の電気炊飯器に鉄道模型…ベンチャーだったソニーが生んだ「失敗作」












