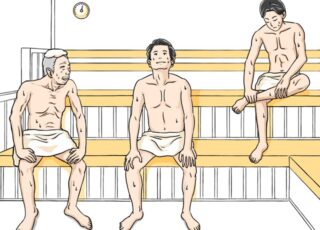「当たり前を疑ってみようと伝えたい」児童文学で作家デビューした新聞記者

新聞記者として働きながら児童書を執筆し、文学賞の選考会で高く評価されて作家デビューを果たした男性がいます。共同通信社の政治部で働く蒔田浩平さん(39)です。
出版した本のタイトルは、『チギータ!』(ポプラ社)。卓球のレシーブ技術「チキータ」をもじったもので、引っ込み思案だけれど、卓球が大好きな小学5年生の少年が主人公です。クラスのレクリエーションの時間に何のスポーツをするかを決めるとき、多数決で選ばれるのはいつも、仕切り屋の男子たちが推すバスケットボールやサッカーばかり。卓球だってやりたい! と、“小さな声”を投票結果に反映させるための大作戦を考える──というストーリーです。
子どもたちの感情の揺れを細やかに描きながら、そこで問うているのは「多数を優先する仕組みは人を幸せにするのか」「真の平等とは何か」といった民主主義の課題。そのギャップから、児童書を出版するポプラ社主催の「ポプラズッコケ文学新人賞」で2017年、最終選考に残り、「テーマの選定に新鮮さがある」「いわゆる運動クラブものとは趣を異にしているのが興味深い」と注目を集め、2019年の春、同社から出版に至りました。
なぜ「政治×児童文学」というアイデアが生まれたのでしょうか。背景には、「民主主義からこぼれ落ちてゆくもの」に対する、割り切れない思いがありました。

“民主主義”からこぼれ落ちてゆくもの
──記者が自身の記事をまとめて書籍化したり、本業の一環として専門分野について書き下ろしたりするケースはよくありますが、「児童文学」とは珍しいですね。
蒔田:今年で6歳になった息子がいて、彼に何か形になるものを残したい、と思ったんです。これまで記者としてたくさんの記事を書いてきたけれど、それは彼のために書いたものではないし、どこかにまとめられているわけでもない。何より、人間っていつ死ぬか分からないですしね。作曲できる人は音楽を残すだろうし、詩をつくれる人は詩を残すだろうけど、自分にできそうなことを選んだら、本を書くことだったという感じです。
──主人公が、バドミントンやラグビーなど、クラスではマイナーな種目を密かにやりたいと思っている“少数派”に協力を求めながら“票”を集めていくシーンは、さながら政権を奪取しようとする野党のようです。
蒔田:自分が小学生だったとき、議論と投票の結果はいつも、積極的に発言する男子児童がやりたいと主張したスポーツ。当時は「型どおりのやり取りをして、“主流派”でなければ意見は通らず、投票で決まったことには納得して粛々とやる」ということに疑問を持ちませんでした。でも、大人になって振り返ったら、なんだかもやもやして。
私は少年野球のチームに入っていたので、「野球をやりたいです!」と言っていたのですが、女子から「野球は危ないと思いまーす」と返されたらそのまま引き下がって、野球は投票の対象にもならなかった。卓球をしたいという子がいても、耳を傾けなかった。女子児童の数は、そもそも男子より少なかった。
形の上では「みんなの意見を聞きます」「多数決で決めます」と、いかにも多様性を尊重した、平等なプロセスに則って決めるかのように言うのだけれども、そこにはさまざまなパワーが働いていたり、不平等な前提があったのを見過ごしていたりしたんですよね。あのとき、もう少しちゃんと考えたり、工夫したりすれば、1回くらいは卓球だってできたんじゃないかな、という思いを形にしたつもりです。

──しかし、少年の目的は途中から「レクで卓球の時間を勝ち取る」ことではなくなり、意外な結末に導かれてゆきますね。このストーリー展開には深みを感じます。
蒔田:「多数決で決めたことに従うのが民主主義だ」という考え方に違和感を覚えるんです。「1回の投票で多くを握ったほうが正しい」としてしまうと、どうしてもこぼれ落ちてしまうものがあるから。
もちろん、例外にばかり目を向けていたら物事は決まりません。でも、本来、民主主義の腕の見せどころや政治の真骨頂というのは、議論の過程でいかにマイノリティの意見を汲み取り、それを活かしてゆくかという点にあると思うんです。「多数者の専制を敷く」ことではなくて。
何がベストなのかを常に考えながら、バランスを取り続けるのは苦しいですよね。でも、「民主主義」にしても「多数決」にしても、過去のさまざまな制度やルールと比べたらベターなだけで、決してベストじゃない。何にしても「これが絶対に正しい」と決めつけないで、本当は何が一番いいんだろう、ということを考え続けなければならない。
だから、「当たり前」を疑ってみよう、ということを伝えたかったんです。思考停止せずに考え続けることが大事なんだよ、というメッセージを物語にできたらな、と。われわれ大人も同じです。選挙が終わった後も、ちゃんと考えていかなければならない。日々、国会や政治家を取材するなかで、自然とそういう考えが熟成されたように思います。

──「当たり前を疑ってみよう」というメッセージを伝えるうえで、フィクションという形式を取ったのはなぜだったのでしょう。
蒔田:記者が仕事で書く文章って、(書き方や盛り込むべき要素が決まっていて)制約がすごく多いですよね。例えるなら、風のまったくない屋内プールを決められた泳法で速く正確に泳げ! という感じで、ちょっとでもコースを外れると監視員がピピピピピー! って笛を吹いて、「こっちに正しく!」と叱られる、みたいな。
もちろん、記者としてその仕事をやり遂げたいという目標は常にあるのですが、ときどき、プールじゃなくて海に出たくなったという感じです。文章表現をもうちょっと自由に、ある程度、自分の責任でやってみたいな、と。
大人だっていつも「夢中になれる何か」を探している
──記者の仕事が自分の外側に書くべきことを見出すものとすると、フィクションを書くのは自分の内側を探っていくこと、とも言えるように思います。実際に書いてみて、どんな経験でしたか。
蒔田:あれほど純粋に何かに打ち込んだ時間は久しぶりでした。大人になると、1つのことだけを考えて最後の一滴まで自分を振り絞るような集中の仕方って、あまりしませんよね。私は何かに打ち込み過ぎると反動が来るので、常に8割くらいの力で走り続けて、なるべく遠くまで行きたいと思うタイプなんです。「命を燃やし尽くす」とか「自分の限界がどこまでかを見極める」という言葉はしっくりこない。特に、仕事ではチームのために結果を出したいと思うと、安定したパフォーマンスを優先したくなる。
でも、小説を書いている間は思いがけず、「表現すること」だけにのめり込んでいる感覚です。もちろん、途中で「賞を取れるだろうか」とか「本として出版できるだろうか」といった雑念がむくむくと出てきて、「とてつもない時間の浪費をしているんじゃないか」と不安に襲われることはあります。それでも、「とにかくこれを書きたい」という思いで突き進んでしまう。もしかしたら、子どものころのように夢中になれる何かを、いつも心のどこかで探しているのかもしれません。

──不安や孤独感に足をすくわれずに書き続けられるくらい、没頭できたんですね。
蒔田:中学1年生のときに1年間、「ものすごくひとり」だったことがあって、あのころから、自分が感じたことや考えたことを文章にする癖がついたように思います。
家庭の事情で埼玉から東京の学校に転校したら、うまく馴染めなかったんです。いじめられていたわけでもないし、友だちも少しはいたのですが、これまでの環境との些細な違いから疎外感をぬぐえなくなって。
例えば、当時は埼玉と東京でも子どもたちの流行に時差がありました。それまで流行りの髪型はスポーツ刈りであり、パンツはブリーフが当然だったのに、引っ越した先ではイケてる男子の髪型はツーブロックの真ん中分けで、パンツはトランクス。ブリーフなんて信じがたい、という感じで(笑)。そうしたギャップにカルチャーショックを受けて萎縮してしまったんです。
それで埼玉の友だちが懐かしくなり、夏休みに会いに帰ったら、なんとツーブロックとトランクスになっていた。ほんのわずかな時間に、流行の波が埼玉にも来ていたんですね。自分だけ時間の流れの中で取り残されたような気持ちになりました。しばらくは笑わないし、登校しても帰るまで席を立たないくらい、暗い生徒でした。
結局、時間とともに心がほぐれて新しい世界に適応し、卒業するころにはまあまあ楽しく過ごせるようになったのですが、あの1年間は自分の内側にぐぐっと入っていって考えることが多かったですね。読書感想文を何通りも書いて、一番、出来がいいものを提出するほど文章にこだわったりしました。今思えば、すごく貴重なひとりの時間でした。
──表現を追求するというのは、ひとりの世界を深めていくような感覚なのでしょうか。
蒔田:いや、それが実はそうでもなくて。特に、今回の『チギータ!』は自分ひとりで書いたという意識がまったくないんですよ。
なんというか、最終的に筆を執ったのは自分だけれど、それまでには色々なことを気付かせてくれた人が、小学校のころのクラスメイトをはじめ、たくさんいて。そんなふうに昔のことを思い出したときに「あれ、もしかしてあのころ、こういうことをみんなも感じていたんじゃないかな?」という気づきがなんとなく降ってきて、それをまとめたのが偶然にも自分だっただけ、というような。
だから、「次はどういうのを書きたいですか」と聞かれても、うまく答えられないんですよね。周りのみんなに書かせてもらったという意識が強いので、「書けます」と簡単には言えない。むしろ、いつか「こういうのが書けるんじゃない?」という誰かの思いがパスされてきたとき、ちゃんと受け取って形にできるように自分を整えておかなければ、という感じです。
そのためには日々、きちんと食べて、ぐっすり寝て、ちゃんと遊んで、児童文学の勉強もして、政治記者としての仕事をしっかりやって。そんなふうに真面目に目の前のことに向き合っていくことが大事なんだろうなと思っています。
この記事をシェアする
「ひとりで作る」の記事

物語は何かを「納得」するためにある〜時代小説「編み物ざむらい」横山起也さん

「意識が戻るときに見る光の世界を描きたい」アーティストGOMAの紡ぐ世界(後編)

ドクロをモチーフとする唯一無二の陶芸家の挑戦「陶芸をもっとゆるーく楽しんでほしい」

迷作文学がズラリ! ひとりの切り絵画家が生みだす「笑えるブックカバー」が超人気

「時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?」国会議員に聞いてみた理由

「ひとりで全部できちゃうんじゃない?」映像ディレクターが見つけたウェブシネマの可能性

手芸なんかやって、意味あるの? 猟師さんの話から考えてみた

耳の聞こえない監督が撮った災害ドキュメンタリー「聞こえる人に心を閉ざしていた」

タイムラプスは「四次元の旅」 運とカンが頼りのワクワク感がたまらない