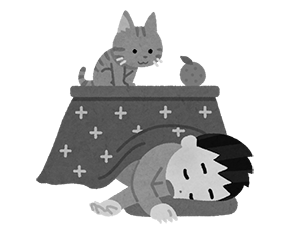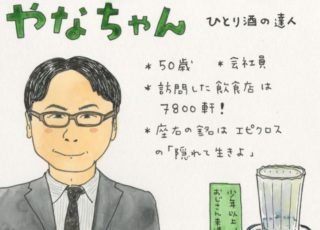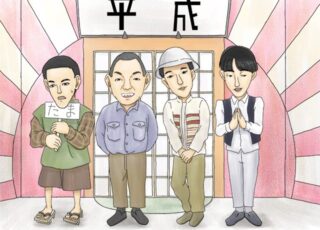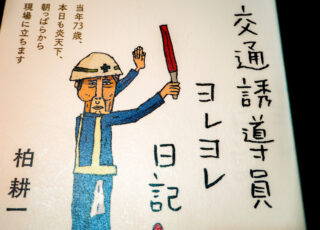その島の空気ごと持ち帰ってほしい 「離島の本屋」をめぐる旅の魅力

ただ、本屋を紹介しているだけじゃない。風土記のような地域の記録であり、生活の記憶であり、旅のガイドブックでもある。本屋が少なくなっていく中で、あえて”島の本屋”に着目した本。それが『離島の本屋 ふたたび』(ころから)だ。
著者の朴順梨さんは、屋久島や種子島、佐渡島、沖縄本島など、全国の”離島の本屋”を訪ね歩いて、そこで感じた驚きや発見を丹念にまとめた。本書を読めば、人との出会いと同じように、本屋との出会いもまた一期一会であることがわかる。
もともと、NPO本屋大賞実行委員会が発行するフリーペーパー『LOVE書店!』の連載をきっかけとして、2013年に第一弾の『離島の本屋』が出版された。その後、連載はウェブメディア「DANRO」に移籍して続き、2020年10月に第二弾として本書が完成した。
「離島の本屋」をめぐる旅の魅力について、朴さんに聞いた。
本だけでなく野菜や雑貨もある
──朴さんにとって、「離島の本屋」の魅力とは何でしょうか。
ひとつは、書店以外の機能があるところです。本だけでなく、野菜や雑貨を売っていたり、自転車の修理やOA機器のメンテナンスを請け負っていたり。本+「何か」があるんです。
素敵な宿に泊まって、温泉に入りながらのんびりするのも、旅の醍醐味だけど、島の本屋には、生活に身近なものが売っていて、地元の人がそれを買いに来る。そこから島の人たちの生活が見えてきます。
連載のはじめ、伊豆大島の本屋に行きました。どういう人が来て、どういう話をしていくのか。お客さんが私にどういう話をするのか。数時間の滞在でしたけど、そういう光景を見ているだけで、心が惹かれましたね。じゃあ、ほかの島はどうなっているのだろうかと。
──本屋はどうやって見つけるのですか。
2006年に『LOVE書店!』の企画が立ち上がったとき、「じゃあ、行ってきて。以上」という感じでした。その先はだれも教えてくれず、編集者がリサーチしてくれることもありません。ネット上にも情報がなくて、はじめのころはタウンページで本屋を探していました。まさに徒手空拳でしたよ。

──ネット情報もだいぶ充実してきたんじゃないですか。
離島の本屋について調べようとすると、自分が書いた記事が出てくるし、人づてに聞いてもほとんど出てこなくて・・・読者から「うちの島にも来てください」というリクエストはあるけれど、どこの本屋に行けばいいのかわからない。今でも手探りですよ。
最近は、グーグルのストリートビューなどで、店の佇まいを確認して、「なんかよさそうだな」とか、「◯◯書店」というところは「あ、これは昔から本屋さんなんだろうな」「個人経営なんだろうな」とか。まあ、カンみたいなものですね。
ただ、ネットで探していると、もうこの世に存在しない本屋に出くわしたりします。検索で見つけた素敵な本屋に行ってみたいと思って、知り合いに聞いたところ、とっくの昔に閉店して、建築会社の資材置き場になっていました。ネットを過信してはいけませんね。
屋久島に行っても「縄文杉」は見に行かない
──離島への移動は、よくフェリーを使われているようですね。旅のコツはありますか。
フェリーでは、とにかく携帯の充電をするため、コンセントの近くでパーソナルスペースを確保することですね。あとは、たまにデッキにあがって、海をボーッと見るくらいで、酒も飲まず、本も読まず、ひたすら寝て過ごしています。
この記事をシェアする
「ひとり旅」の記事

スプリングスティーンの手は分厚くて温かかった(渡米ライブ紀行 4)

ライブ会場に入れない!? 想定外のトラブルに戸惑う(渡米ライブ紀行 3)

70代とは思えないパワフルな姿に圧倒された(渡米ライブ紀行 2)

想い焦がれたミュージシャンを観るためアメリカへ(渡米ライブ紀行 1)

目的は「東北を走ること」 無計画の3泊4日ソロツーリング
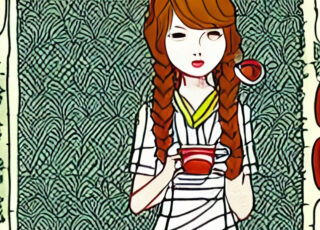
茶道に恋した旅人(AIショートノベル 1)

AIが「ひとり旅」のエッセイを書いたら?

福島の「原子力災害伝承館」その周りには「なんでもない土地」が広がっていた

初心者がソロツーリングを楽しむ方法!「屋久島ひとり旅」で学んだこと