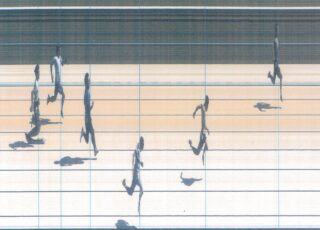フリーランスは「アコムが友達」 キャリア20年のライターが語る「お金」の話

若者の自殺や生きづらさを長年取材し、10冊以上の著書があるジャーナリスト渋井哲也さん。大学卒業後、新聞記者になりましたが、30歳になる少し前、安定した収入の新聞社を「衝動」で辞めて、フリーランスのライターになりました。
それから20年。フリーライターとして、どのように仕事を得て、いくらぐらいの収入を得てきたのでしょうか。これまで会社員に戻りたいと考えたことはなかったのか。そしてなにより、会社員でいたころよりも、魅力的な生活を送れているのでしょうか。
渋井さん自身が開いた「フリーランス20周年記念」のイベントで、話を聞きました。
新聞社時代の年収は「400万円にいくかどうか」
ーー今回フォーカスしたいのは「フリーランスとお金の関係」です。渋井さんはフリーになる前、新聞社の長野日報に記者として勤めていたということですが、その頃の給料はいくらぐらいでしたか?
渋井:はっきりと覚えていないです。覚えているのは、新聞労連(日本新聞労働組合連合)加盟社のなかで、ビリから2番目くらいに安かったということです。
ーーボーナスも安かったのですか?
渋井:「モデル賃金」というのがあるじゃないですか。35歳で、子供が2人いるみたいなモデルがあって。当時(20年前)、そのモデル賃金が新聞社で一番高いところでボーナスが100万円くらいあったんですけど、うちは30万円でした。年収はたぶん、400万円にいかないぐらいだったと思います。
ーーそれくらいの給料で、生活していくのは問題なかったでしょうか。
渋井:長野日報は本社が長野県諏訪市にあるんですけど、諏訪市の会社の基準で考えれば、平均よりやや上くらいだったと思います。長野県で暮らす場合、年収300万円あれば充分でした。
ーーフリーライターのなかには、学生時代から就職せずライターを続けている人もいますが、渋井さんの場合、最初は「会社員のほうがいい」という考えがあったのですか?
渋井:「最初は」というより、最初で最後のサラリーマン生活だと思っていました。会社を辞めることはないと思っていたので。
ーーではなぜ、新聞社を辞めてしまったのですか?
渋井:衝動です。「辞めたい」と思ったんですよね。衝動が生まれたベースには、松本サリン事件(1994年)や阪神大震災(1995年)があります。大きな事件があったにもかかわらず、メディアが有効に機能していなかったという事実と、周りがだんだん辞めていったということがありました。

ーーその時点で、転職ではなくフリーでやろうという意識だったんですか?
渋井:そうではないです。先輩はほとんどが中日新聞とか、読売新聞に転職していました。中日新聞に転職する人が多いので、うちは「中日新聞の専門学校」と呼ばれていたくらいです。会社を辞めた当時は、オウム事件が終わって、その残党が長野県にいて、自治体が裁判を起こしていました。それを追っかけていましたね。そんな風に記者時代に追っかけていたものを「どこで書こうかなあ」みたいな感じで。ただ、それは、フリーライターになろうと思ってやってたわけではないんです。
ーーどういうことでしょう?
渋井:いまの状況をつなぐとか、せっかく取材が進行しているから追っかけたいという感じです。「フリーライターになる」という意識が生まれたのは、信州大学の小泉典章先生(現・長野県精神保健福祉センター長)という方がいて、その小泉先生に相談したときです。「子供に直接関わる仕事をするのと、子供に関わることを伝えていくのと、どっちがいいと思いますか?」って。すると「子供に携わる人はたくさん出てくるけど、現場を伝える人はなかなかいない」と。「そっちのほうがいいんじゃないか」って言われたんです。
金銭的にキツかったのは震災3年後 精神的にキツいのは「いつも」
ーー知人のアドバイスにしたがって、教育を支援する仕事ではなく、それを伝える側になろうと考えたと。それから20年間フリーでやってきたわけですが、途中で就職しようと思ったことはありますか?
渋井:ありますよ。最初は35歳くらいですかね。
ーー会社を辞めて7、8年たったころですね。それはなぜですか?
渋井:周りのフリーライターの人たちの雰囲気では、「35歳くらいまでに売れなかったら正社員じゃないの」みたいな感じがあって。

ーーフリーとして一本立ちできなければ、社員に戻ったほうがいいと。
渋井:そうそう。知り合いの編集者とゴールデン街で会ったとき、フリーでやっていたはずなのに35歳で社員になっていた。そういうモデルもいたんで。
ーーということは、渋井さんは「一本立ちできていない」と考えていたんですか?
渋井:どこまでを「一本立ち」と考えるかですよね。仮に年収300万円だとして、300万円で満足して一本立ちと考えるのか。それとも400万円で一本立ちとするのか。ただ当時は、自分のなかで「食えてない」という意識がありました。
ーーしかしフリーランスを続けたということは、就職していないということですね。残念ながら、採用にはいたらなかった?
渋井:そういうパターンと、面接の日にどうしても行かなきゃならない取材があって、キャンセルしちゃったのもありますね。
ーー出版社から「社員にならない?」と誘われたというフリーライターもいます。これまで、そういった誘いはありましたか?
渋井:会社を辞める前にありました。辞表を出したという情報がまわったときに、中日新聞から誘いがありましたね。ただ僕、(プロ野球の)中日ファンなんで、ファンのチームの親会社に入るのはどうかなってのがありましたね。それはいかがかと。
ーー以降フリーライターを続けてきたなかで、長野日報を辞めたときの年収より高くなった年と低くなった年とでは、どちらが多いですか?
渋井:売上という点では、高いときのほうが多いですかね。ただ、どれだけを経費と考えるかで、変わってきます。経費まで含めて考えると、超えない場合のほうが多いとも言えますね。
ーーとなると、金銭的に大変な時期もありますか。
渋井:ありますね。そういう場合は先輩にお金を借りたり、「アコム」っていう友達に借りたりしてました。ほかには「セゾンカード」という友達がいたり、「Tポイントカード」、「UCカード」という友達がいたりします。

「酒が飲めなかったら、たぶん仕事がない」
ーー話を聞けば聞くほど、よくやってこられたなあという印象です。
渋井:あるフリーの先輩は借りたお金を返せなくて自己破産しているんですが、僕は自己破産までいってないから、続けちゃうんでしょうね。
ーー逆に続けることができず、フリーランスを辞めていった人はどういう人ですか?
渋井:こだわりが強い人です。たとえば、編集者にいろいろ要望を出されたけど、「そんな単純なもんじゃねえ」と、編集者と喧嘩して原稿が落ちたっていう、ある意味マジメな人は辞めていきます。逆に、あまりこだわりがなくてルーズな人も、やっぱり仕事がなくなっちゃいますよね。
ーー難しいものですね。営業の一環として、編集者やメディアの関係者と飲みにいくことはありますか?
渋井:僕、酒を飲めなかったら、たぶん仕事がないと思います。飲めなくても飲みの席が好きであればいいんですけど、そもそも飲みの席が嫌いだったら、こういう生活は続かないでしょうね。
ーーこれまで続けてきたなかで、一番きつかった時期はいつですか?
渋井:お金という意味では東日本大震災の3年後、2014年、2015年くらいがきつかったですね。出版社からの経費が出ないまま、取材に行っちゃったので。
ーー精神的にきつかったのは?
渋井:それは「いつも」じゃないですか。
ーーそうした不安をどうやって解消しているんでしょう。
渋井:たぶん人に会うことかな。人に会って「みんな食えないんだ」と思うか、あるいは多少食えている人がいれば、それが目標になったりするので。それで自分の状況が改善されるわけではないけれども、そこでフリーライターを続けようとする意識が生まれているかもしれないですね。
この記事をシェアする
「フリーランス」の記事

シリコンバレーで急増する「クラックト・エンジニア」と孤独な熱狂

インタビューは「面白くなくない記事」を書けばいい〜ライター土井大輔さんの取材術

フリーランスの収入を直撃!?「消費税インボイス」の問題点とは?

「眠れなくなるほどキモい」寄生虫の魅力を発信し続ける孤高のライター

50歳でテレビ局を辞めた「フリーライター」どうやって稼いでいるか?

年収1500万円以上の「テレビ局プロデューサー」が50歳でフリーライターに転身した理由

「人は『正しい』を愛するとは限らない」AV業界から東大大学院へ 作家・鈴木涼美さん

留学してフリーランスに『真面目にマリファナ』本の著者に聞く・前編

生理をよく知らないフリーランスの日本人男、アフリカで布ナプキンを作る(ひとり国際協力 3)