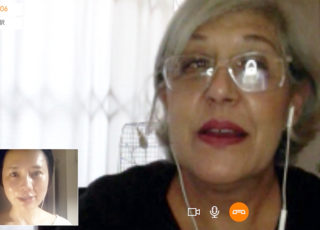「乳がん患者も下着にこだわりたい!」 患者が生み出した華やかな「乳がん用ブラジャー」

乳がんになっても、できないことなんてなかったです。がんになってよかったとまでは言わないけど。転移した人、治療から見放された人に会うたびに、そう伝えたいって思います。私のエネルギーを分けてあげたいって――。
「女性の自由と孤独」をテーマに、女装する小説家・仙田学がさまざまな女性にインタビューするこの連載。今回は、乳がん患者のためのブラジャーを開発・販売しているマユミ(57)に話を聞いた。
立て続けに襲ってきた苦難の数々
「乳がんになったのは7年前。病院で告知を受けたときには、不安でいっぱいになりました。万が一のことがあれば、子どもはどうなる? 仕事ができなくなるなら収入は? 子どももがんになるかもしれない・・・。仕事の帰りに、自宅近くの交差点でしゃがんで大泣きしたこともあります。でも、当時14歳と20歳の娘たちにはそんな姿を見せられないから、軽い感じで伝えました。お母さん、がんになっちゃったよ、って」
23歳で結婚して、その翌年に大手企業に就職して以来、20年以上も会社員として働きながら子育てをしてきたマユミを、数々の苦難が襲い始めたのは40代の半ば頃からだ。
母親が脳梗塞でとつぜん亡くなった。離婚して2人の娘を引き取った。椎間板ヘルニアと坐骨神経痛を患った。勤めていた会社が破綻して別の会社に吸収された。
「乳がんが発見されたのは会社が破綻した直後で、人生のどん底にいると感じました。でも私は根っからポジティブな性格なので、辛いことがあればそのぶん楽しいことが待ってるはず、とも思ってました」
「乳がん患者も下着にこだわりたい」
人生のどん底を経験しながら、希望を失わなかったマユミ。だが、どうしても受け入れられないことがひとつだけあった。それはブラジャーだった。
「術後しばらくは乳がん患者専用のブラジャーが必要になるんですけど、いざ探してみてびっくりしました。色はベージュ・薄ピンク・茶色しかないし、柄もない。おしゃれなブラジャーがなかったんです。乳がんになったことは罪なの?ってくらい。専門店に買いに行ってもネクタイみたいに壁にぶら下げて展示してあるし、試着しても店員が見に来ることもなかったんです」
もともと下着にはこだわりがあり、高価でいいものを選んでいたが、それまでつけていたようなものはなかった。居住地である京都で見つけられなかったマユミは、新幹線で全国の百貨店や下着屋を訪ねたが、希望に叶うものには出会えなかった。
「だから、自分で作ることにしたんです。とりあえず会社名を考えて商標登録をしました。それから有休を取っていろんな下着メーカーに話をしに行ったり、展示会に足を運んでブラジャーを試着しまくったり。自分でつけてみて違和感のないものを探しました。そのうちに、これというものが見つかったので、5枚ほど卸してもらって、業者にお願いして加工したんです」
ネットショップを立ち上げてしばらくすると、最初の客が現れた。住まいが近いからとマユミの自宅までバイクできたその客は、試着した後に「安いし綺麗だし」と2枚を購入して帰った。
試行錯誤を繰り返し、少しずつ販路を拡大していった結果、事業は軌道に乗り始めた。おしゃれで綺麗な下着をつけたい乳がん患者の女性は、マユミの想像以上に多かった。
「女性は気分の上がる下着をつけたいんですよね。たとえば大事な人とデートするときや、仕事で重要なプレゼンがあるときには、そういう下着をつけていたい。お客様には70代の乳がん患者の方もいらっしゃるんですけど、ピンク色のものや花柄のものを買っていただけることが多いんです。明るい気持ちでいたいからって」
「気分の上がる下着をつけていたい」というのは、年代を問わず女性に共通する思いだとマユミは言う。それならなぜ、乳がん専用のブラジャーには、そのようなものがなかったのだろう。
「乳がん専用のブラジャーが開発されたのは40年ほど前ですけど、たぶん開発者が相談した医師が男性だったんじゃないかな。だから機能的には問題がなくても、色や柄は、ないがしろにされたのかもしれません」

行動の源泉に、母の背中
それまでになかったから自分で作る。シンプルな発想だが、それを実行できる女性はなかなかいないだろう。マユミのポジティブさや行動力の源泉を私は知りたくなった。
「子どもの頃はジメっとした子でしたね。自分は不細工だと思ってましたし、コンプレックスの塊でした。でも、いつも前に引っ張り出されるんです。根が世話焼きなんでしょうね。広島の田舎で生まれ育ったんですけど、祭りには男の子しか参加できなかったんです。それが変だと思ったから女の子だけ集めて祭りをやりました」
人に頼られ求められるだけでなく、困っている人を見かけると声をかけずにはいられない。マユミのそんな性格は母親譲りだという。
「母は若くして亡くなったので、私にとっては一生追いつくことも、越えることもできない存在なんです。両親で事業をしていたんですけど、社員たちは父よりも母を慕っていました。45年も前に、当時としては珍しかったのですが、障がい者や中国人の方を雇っていました。家には住み込みの従業員がたくさんいて、14人掛けのテーブルを皆で囲んでご飯を食べてました。ストレスが溜まると海に行ってアサリを取ってきたり、いきなり稲刈りを始めたり。パワフルでいつも笑ってる人でした」
母親が仕事をしていることで寂しさを感じたこともあったが、今思えばその背中を見せてもらっていたのだと感じている。そんなマユミは今、乳がん患者やその家族と積極的にふれあう機会を作っている。
「乳がん患者と、その家族や友達の方を集めてサロンを実施していますが、年に2回は食事会をしてるんです。お昼からお酒を飲んだり、祇園で芸子遊びをしたり。楽しいですよ。普通ならなかなかできないことをするんです。乳がんの女性は、特に地方の人ほど病気のことをまわりに言えなかったりするんです。就職するときにも不利になるから隠してる人も多いですし、辛い思いをしている家族も多いです。だから患者とその家族を、周りの人たちが支えることが重要なんです」
乳がんになってもできないことなんてなかった、というマユミ。現在も3カ月ごとに検査を受けて、転移や再発の恐怖とともに治療を続けながら、乳がんブラジャーの事業に全力で取り組んでいる。同じ乳がんの女性たちにマユミが届けたいものは、ブラジャーだけでなく、前を向いて生きていく力なのかもしれない。
この記事をシェアする
「ひとり仕事」の記事

「10歳のころの自分が笑えるネタか」さかな芸人ハットリさんが大切にしていること

「目撃すれば幸せになれる」とウワサが広がる「自転車で文字を売る男」

個室のない私が「畳半分のワークスペース」を手に入れるまで

ひとりで山を歩き「食べられる野草」を探す 「山野草ガイド」を作る地域おこし協力隊員

「当たればお立ち台、はずれたら死刑台」競馬場で「予想」を売る伝統芸

おじいさんたちに混じり「大工見習い」として働く31歳女性「毎日幸せだと思って生きている」

「どう乗り越えてやろうかワクワクした」危機を楽しむ強さでコロナに打ち勝つ

大学を中退したのは「回転鮨」が原因だった 「出張鮨職人」のイレギュラー人生

「出張鮨」を誰でも楽しめるものに 「スピード命」の型破りな鮨職人