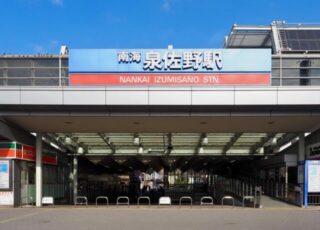都会に疲れたら、神話の島・壱岐島へ「ひとり旅」(壱岐への旅・前編)

忙しい日々に少し疲れたときは、小さな旅に出ることにしています。今回は、壱岐島(いきのしま)にひとりで出かけてきました。壱岐といっても何県かわからないという人も多いのではないでしょうか。私もそのひとりでした。答えは長崎県です。
博多港から高速船で1時間。小さな港には人影もまばらです。車に乗り込み、内陸に向かって走ると、行く手にキラキラと輝く海が不意に現れる瞬間があります。そのとき、ああ、私は今、島にいるのだと実感するのです。

「神社巡り」を楽しめる島
壱岐島は『古事記』にも出てくる神話の島。今回は、その荘厳さを感じたくなってここにやってきました。なにしろ、神話は現代社会とはもっとも遠い存在のひとつですから。
まず向かったのが、「月読神社」。伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が右目を洗ったときに産まれたのが月読尊(つきよみのみこと)で、夜をつかさどる神として、月にたとえられています。この神様がまつられているのが月読神社で、全国各地にあるのですが、壱岐の月読神社は日本最古の神社といわれ、航海の安全を祈るために建てられたそうです。


神話の世界で私がもっとも敬愛するのが天照大神(あまてらすおおみかみ)なのですが、月読尊はその弟に当たります。夜をつかさどるという神秘性になんとも惹かれます。ここでは自分の人生という航海の無事を祈りました。
次に向かったのが、波戸崎という小さな港に向かって立つ塩竈神社。塩土老翁(しおつちのおじ)がまつられていますが、この神社も航海の安全を祈るために建てられたとのこと。どこに行くにも港から船を出すしかなかった壱岐の人々に必要だったことがわかります。


このように神社巡りを楽しめる壱岐島なのですが、実は日本でもっとも神社の密度が高い地域といわれています。その数は、公式には150あまり。小さなものも入れるとなんと1500にも及ぶのだとか。
神話の柱を見に行くクルーズ
この日のハイライトはサンセットクルーズ。クルーズとは言っても、6人乗りの小さな船を地元の有志が出してくれるというものです。夕陽の沈む時刻の少し前に出航しました。

このクルーズの見どころも、神話に基づいています。壱岐島はその昔、あちこちへ動いてまわる「生き島」だったので、流されてしまわないようにと神様は島を囲むように8本の柱を立ててつなぎ止めたといいます。
それぞれの柱は折れてしまい、今は岩として残っていると言われているのですが、その柱の1つであるとされる岩を見に行こうというのです。

この日は少し風があり、小さな船は右に左に大きく揺れました。その揺れもアクティビティとして楽しみながらどんどん沖に出ていくと、目指す岩が現れました。その岩とは、壱岐の観光地のひとつである「猿岩」です。
壱岐に訪れた人は必ず向かうという景勝地である猿岩ですが、海上から見たことのある人はなかなかいないとのこと。島から見ても猿にそっくりのユーモラスな形をしたこの岩、海上からもしっかり猿の形に見えました。


あいにくどんどん雲が出てきてサンセットを眺めることはできなかったのですが、海から神話を感じるという貴重な経験となりました。
天上世界へ向かう柱
神話はこれだけにとどまりません。壱岐島は天比登都柱(あめのひとつばしら)という別名を持ち、これは「天上につながる一本の柱」という意味なのだそうです。
天比登都柱は世界の中心を表し、天地を繋ぐ道を意味するという説があるといいます。『古事記』以前には、壱岐から柱伝いに天上世界へ行くことができると信じられていたという話も聞きました。
今の私にとって天上世界とは、すなわち心安らぐ時空のこと。この島に来て神話の世界に身を浸したことで、少し心穏やかな気分になれたと感じる壱岐島の1日でした。


【壱岐への旅・後編】海の幸と温泉を堪能、長崎県・壱岐島への「ひとり旅」
この記事をシェアする
「ひとり旅」の記事

スプリングスティーンの手は分厚くて温かかった(渡米ライブ紀行 4)

ライブ会場に入れない!? 想定外のトラブルに戸惑う(渡米ライブ紀行 3)

70代とは思えないパワフルな姿に圧倒された(渡米ライブ紀行 2)

想い焦がれたミュージシャンを観るためアメリカへ(渡米ライブ紀行 1)

目的は「東北を走ること」 無計画の3泊4日ソロツーリング
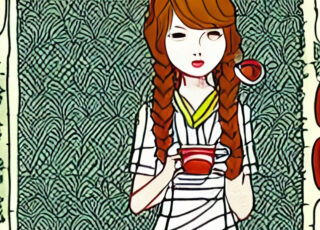
茶道に恋した旅人(AIショートノベル 1)

AIが「ひとり旅」のエッセイを書いたら?

福島の「原子力災害伝承館」その周りには「なんでもない土地」が広がっていた

その島の空気ごと持ち帰ってほしい 「離島の本屋」をめぐる旅の魅力