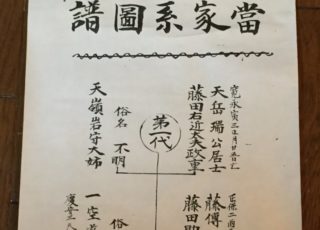スポーツ無縁、貧血気味のインドア女がサーフィンの虜になったワケ

20歳の時、さして仲良くもない大学のクラスメート3人とノリでタイに行き、三日目で大げんかして以来、旅はひとりと決めている。
ひとり旅は清々しい。眼に映る景色の中に、私の知ってるものがない。そのことが私を心からくつろがせる。あらゆるフィルターの剥ぎ取られた、つるつるの生娘みたいな世界が目の前に転がっている。
あらゆる重力から解き放たれる快感
サーフィンの旅を始めたのは4年前だ。AV監督の代々木忠さんとお会いした時、開口一番「みゆきちゃん、サーフィン始めたらセックス良くなるよ!」と言われたことがきっかけだ。
当時の私はなまっちろい、貧血気味のインドア女で、日焼けなんてもってのほか、屋外のスポーツとはまるで無縁の生活を送っていた。しかし、言われたことはとりあえずやってみる性格である。その言葉を鵜呑みにし、早速次の週、サーフレッスンを予約して千葉の海へと繰り出した。
初めて波に乗った時の驚きは今でも忘れられない。
あらゆる重力から解き放たれる快感。脳が頭から飛び出して、宇宙に散り散りになってゆくような陶酔。見渡す限りの大海原、広大な空にサンドされ、自分の体の細胞一粒一粒が自然と一体になるような安心感。
その代償としての、一歩間違えれば死んでしまう恐怖。命のあり方の根源が海底深くからせり上がってくる。まるで、大きな大きなお母さんのお腹の中にいるみたいだ。
その日から私は波の虜になった。東京から2時間かけて電車で千葉の海に週2回通いつめ、マイボードとマイウェットを購入した。駆け出しのライターには痛い出費だったが、心は燃えていた。
車もない。バイクもない。ふうふう言いながらサーフボードを電車に詰め込み、早朝に移動する。日焼けも運動も大嫌いだった女が、人生初の日焼け痕を作り「人間、ちょっとは焼けた方が健康的だよね」と言い訳までするようになった。
サーフィンは弱肉強食で男女平等

始めてみてわかったことだが、サーフィンは一見、すごぉく「男社会」なスポーツである。
サーファーはみんな、筋骨隆々の日焼け男だし、波は一本につきひとりしか乗れないルールなので、海の上では波の取り合いになる。そんな時、競り勝つのはやっぱり「おい姉ちゃん、わいが何年、波の上にいると思っとんのや」って感じの眼光鋭いマッチョサーファーである。初心者の、特に女なんかタジタジだ。
しかし、それは裏を返せば、男も女も関係のない実力主義の世界だってこと。波の上では弱肉強食、男女平等、上手い奴が正義。どんなにいかつい男性も、上手い女性には波を譲る。
ハワイのボウルズでは、巨大ボードにまたがったキングコングみたいなローカルレディが抜群のボードさばきで男性たちをびびらせていたし、バリのスランガンでは、4歳から波に乗ってる、っていう現地人の女の子が、観光客の白人サーファーやバリ人の男たちを蹴散らしてとんでもなく優雅なライドを見せていた。

考えてみれば、男女が全く平等に、同じフィールドで競り合えるスポーツってそんなには多くない。海の上の女性たちの、あらゆる属性から解放された、気持ち良さそうな笑顔ったら!
腕一本で大海原に乗り出し、波を捕まえて、自分史上最高のライドをする。そのことにかけては、男も女も、年齢も関係ない。
男性編み物アーティストの横山起也さんに以前お会いした時、彼はこう言っていた。「夢中で何かを作ってる時って、男とか女とか考えないでしょ?」って。それと同じで、「夢中で何かに取り組んでいる時って、男とか女とか考えない」のだ。
あらゆる陸のしがらみから解かれ、板一枚を挟んで海と一体になる心地よさ。その代わり、一歩間違えたら死ぬスポーツでもある。可愛子ぶりっ子したって、海の上では誰も守ってくれない。自分の肉体しか信用できない。
夢中で波を追いかけ、巻かれ、泡に沈み、それでもなにくそ、と沖に向かって腕をかく時、地上で32年間、蓄積してきた個人の属性が、タグ付けが、性的アイデンティティーが剥がれ落ちてゆく。波が、海が、あらゆる地上のジェンダー的な役割から、私を解放してくれる。
サーフトリップでないと出会えなかった最高の景色

一番忘れられないのはハワイのシークレットビーチだ。ローカルの友人に連れて行ってもらった辺鄙(へんぴ)な海沿いの公園で、テトラポットを踏みながら降りていった先には信じられないようなコバルトブルーの静かな海が広がっていた。私たち以外には誰もいない。「観光客はみんなワイキキ・ビーチに行きたがるけど、ハワイにはこういう”小さな宝石”がたっくさんあるんだよ!」と彼は笑った。
日差しを浴び、適度に焼けた後でローカルしかいない食堂に入り、ガツガツかき込んだアヒポキ丼は、心も体も胃袋から海と一体化したみたいで最高に美味しかった。

サーフィンをしていなかったら絶対に出会わなかったような素敵な景色に出会えるのも、サーフ旅の魅力である。
フィリピンのサン・フェルナンドビーチも最高だった。日本人はほとんどおらず、ヨーロッパのバックパッカーたちが注目しているビーチで、海の上にはローカルのサーファーばかり。

だだっ広い薄青いフィリピンの海には、ポツポツと人影が浮かぶばかり。ワイキキビーチで初心者と波を取り合うくらいなら、ちょっと時間をかけてここに飛んでくる方が100倍いい。フィリピンのお気楽な黄色い太陽の下、自分たちしかいない海を独り占めできるのは最高だ。

フィリピーナは明るく陽気で親切だし、どこまでも続くロングコーストでは、ビーチに出さえすればたった1000円でサーフボードが借りられるし、2000円でインストラクターによるレッスンが受けられる。「お金がないけどサーフィンしたい!」という冒険好きにはぴったりの場所。ヨーロピアンが多いせいか、おしゃれなレストランが海沿いに並んでいて、チルアウトするには最高だ。1週間は沈没する価値あり。

浮世のしがらみからの解放
これまでは新品でサーフボードを買うとなると10万円以上のものが主流だったが、最近はソフトボードの流行で、安くて軽いスポンジ製のボードがたくさん出回っている。柔らかく、ハードボードに比べて安全なので、女性でも気軽に始められる。
最高の波に乗った後のサーファーは口を揃えて言う。「生きてるってこういうこと!」
仕事で、プライベートで、にっちもさっちもいかなくなって疲れ果てた時、私はサーフボードを味方につけてふらりと旅に出る。
波にあらがい、泡に巻かれ、裸の心で自然と向き合ううち、つまんないジェンダーロール、社会的役割、アイデンティティーが剥がれ落ち、いつのまにか浮世のしがらみなんて抜け落ちる。
その時私はちょっとだけ、自分が最強無敵になった気になる。
そして、その気分は陸に戻った後にだって、かすかに残る日焼けの跡と共に体と心の底に留まり続けるのだ。
この記事をシェアする
「ひとり旅」の記事

スプリングスティーンの手は分厚くて温かかった(渡米ライブ紀行 4)

ライブ会場に入れない!? 想定外のトラブルに戸惑う(渡米ライブ紀行 3)

70代とは思えないパワフルな姿に圧倒された(渡米ライブ紀行 2)

想い焦がれたミュージシャンを観るためアメリカへ(渡米ライブ紀行 1)

目的は「東北を走ること」 無計画の3泊4日ソロツーリング

茶道に恋した旅人(AIショートノベル 1)

AIが「ひとり旅」のエッセイを書いたら?

福島の「原子力災害伝承館」その周りには「なんでもない土地」が広がっていた

その島の空気ごと持ち帰ってほしい 「離島の本屋」をめぐる旅の魅力