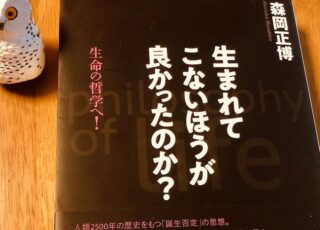「人間は恐ろしい」 人嫌いの50代写真家がそれでも「群集写真」を撮るワケ

写真家の小野寺宏友さん(58)は、東京の群衆を撮影しています。今年の夏だけでも6つの花火大会と6つの盆踊りを撮影しました。その他にも映画の野外上映や渋谷ハロウィンなど人の集まりそうなイベントがあれば、持ち前のフットワークの軽さで、どこへでも撮影に行きます。
そんな小野寺さんですが、実は人間嫌いで人混みは大嫌い、祭りなんてもってのほかなのだとか。なぜ小野寺さんは、群衆を撮影することになったのでしょうか。小野寺さんの半生に迫ります。
とにかく人間が恐ろしかった
小野寺さんは、「写真家」と「カメラマン」は全く違うと言います。
「人に頼まれて、生活やお金のために行う撮影は『カメラマン』の仕事。それに対して『写真家』の仕事は、内側から沸き上がってくる『これを撮らなければ俺はダメだ!』という衝動に駆られてシャッターを切る、そういうものだと思っています」
フリーの「カメラマン」として活躍していた小野寺さんは、特撮や女児向け人形の撮影などで才能を発揮、1995年には映像監督として指揮をとる立場になりました。しかし、周りとのコミュニケーションはうまくいかなかったと言います。
「とにかく人とぶつかってばかりでした。頑固なところがあって、『俺はこうやるんだ』と押し通してしまう。人に何かを伝えるのも下手くそで」
ある日、大型の案件が終わると、心身の疲れからか体調を崩した小野寺さん。高熱を出して2週間入院しました。
「病気から復帰すると、仕事がほとんど無くなっていました。仕事関係者と会えば、『あいつがお前のことを悪く言っていたぞ』なんて耳に入ってきて、『オレ、全員に嫌われていたのでは?』と思ってしまいました。
そこからはずっと、人生の暗黒期でしたね。生きる気力を失い、少ない仕事をこなしながらも、なるべく人と接しないようにしていました。精神科にも通い、『どうやって死のうか』と毎日のように考えていました」
実は昔からコミュニケーションが苦手だったという小野寺さん。「とにかく人間が恐ろしかった」と振り返ります。
「子供の頃から、人と話すと『自分の感覚と全然違う』と感じていました。上手く意思疎通ができず、普通に接していたつもりなのに相手が突然物凄い剣幕で怒り出したりする…。それはとても恐ろしいことでした」
自分を投影した写真作品

その後、小野寺さんは長い間生きる気力を失っていましたが、ある日転機が訪れました。
「2002年の暮れ、旧ソ連の面白いトイカメラに偶然出会って、撮りたいという意欲が急に湧いてきたんです。そこで何を撮るべきか考えていたときに、近所の酒屋が潰れて、取り壊しのパワーシャベルが目に入りました。それを何だかかっこいいと感じて、深夜に三脚を立てて撮影してみたんです。そこでスイッチが入りました」
それから小野寺さんは毎晩のように撮影に出かけるようになりました。公園の遊具、工事現場にたたずむ重機、つたの絡まった警報機…。人々が寝静まった街でそうした「モノ」を撮り続けました。
「ある日、訳も分からないまま撮ってきた写真達を並べ、眺めました。何でオレはこんなものを撮っちゃうのかな…って考えたんです。自分の心の中にダイブしたら、その理由が分かりました。それぞれの写真の共通点は、『明日、誰かの役に立つのを待っているモノたち』だったんです。遊具は明日、子供達に遊んでもらうために。重機は工事のおっちゃんを乗せるために。つたの絡まった警報機だって、明日役に立つのを待っています。あ、これ、オレ自身の姿じゃん…って思いました。仕事も生きる気力もなかった自分を投影した、ポートレートだったんですよ」
こうした小野寺さんの作品は、個展「シンヤノハイカイ」で発表されました。「今は仕事がないけれど、俺はまだできるんだぜ」という、小野寺さんの静かな表明でした。


明日への希望を写真に写す
2004年には、写真集「彫刻水路都市」の制作を始めました。都内の水路を辿り、上流から下流まで全く同じ構図で撮るという試みで、鏡のように風景を映す水面を撮るため、必ず快晴の日に無風の状態で撮影されました。
「渋谷川という川は、初めは水がないんです。でもずっと下流へ向かうとしだいに水がでてきて川になって、海へ続いていた。死んでいるようにみえても生きていて、ちゃんと海まで繋がっている。都市河川の持つ生命力ってすげえな!と気付きました」
死んでいるようでも、生きているーー。それもまた寓意的で、小野寺さん自身を投影した肖像画のような作品でした。


また小野寺さんの写真の多くは深夜に撮影されていますが、その理由については次のように話しています。
「深夜って一人静かに撮影できるのも良いですし、恐ろしげな印象ではなく、明日への力を蓄えるための時間帯だと思ってます。日本中が希望で満ち溢れてる時代を生きた昭和35年生まれの僕には、『明日』って希望の象徴なんですよ」

「群集」を撮る理由とは
ずっと無生物ばかりを撮ってきた小野寺さんですが、あるときから人の集合体である「群衆」を撮影するようになります。そこには「写真家」としてのジレンマがありました。
「SNSなんかを見ていると、反響が大きいのは人がカメラ目線で写っている写真です。人との関係性を上手く築けない僕は、人間なんて恐ろしいものよく撮れるな、と感じてしまうんですけど、人を撮らないって写真家としてどうなのかとおぼろげに思っていました。しかし、僕には他の人達のような撮り方はできない。そこで出た結論が『群衆を撮る』でした。ある集会に参加した際に、引いた視点で人々を撮ってみたら手応えがあり、こういうのなら人を撮れると感じたのです」
小野寺さんは、「群衆」を「群集」と表記します。「群衆」は人の集まりを指す名詞ですが、「群集」は人以外も含み、動詞にもなります。
「宇宙人が地球人の観察をするような視点ですよね。群集という現象そのものを、俯瞰して撮っています。僕の撮る群集は、モノクロです。群集の中に入れない僕にとって、そこに色はなくモノクロのように見えるんです。その感覚を、そのまま写真の表現に生かしています。
花火の群集撮影に行けば、浴衣を着て花火を観るカップルや、両親と手を繋いではしゃぐ子供達が居ます。僕はそんなハッピーな群集の一員にはなれないし、家族もいないひとり者ですが、楽しんでいる人達を見ると、こちらもハッピーな気分になったりします。その場にその人達が集まるのはその時限り。僕はその時間を写真に収めます」

「群集」と「ひとり」
東京生まれの小野寺さんは、群集を次のように捉えます。
「一駅離れると、そこに居る人の趣味嗜好が全く違う東京という都市を、とても奇妙で興味深いと感じていました。例えば、原宿に集まるおしゃれな子達は、原宿へ行くことでアイデンティティを示しているのではないかと思います。渋谷、下北沢、銀座…。人の種類が明らかに違います。東京の群集を形作る人達は、世界のすみっこから、好きな場所へ行くことで自分の存在を確認しているのではないでしょうか」
群集になる人々をこのように分析した上で、それでも小野寺さんは群集ではなくひとりでいることを好みます。
「ひとりで生活し、ひとりで撮影する。それが一番、気楽で自然にいられます。ひとりだからこそ自分の世界を突き詰めて、どう際立たせていくかという戦いをしていますね。このまま死んでいくのだったら、とことんまで『ひとり』の存在を示してやろうじゃないかと思います。自分の写真を100年先に歴史の痕跡として伝えたいという思いがあるので、そのために極限まで質にこだわった写真を撮ります。できればオレが生きてるうちに評価してほしいんですけど(笑)」

この記事をシェアする
「ひとり仕事」の記事

「10歳のころの自分が笑えるネタか」さかな芸人ハットリさんが大切にしていること

「目撃すれば幸せになれる」とウワサが広がる「自転車で文字を売る男」

個室のない私が「畳半分のワークスペース」を手に入れるまで

ひとりで山を歩き「食べられる野草」を探す 「山野草ガイド」を作る地域おこし協力隊員

「当たればお立ち台、はずれたら死刑台」競馬場で「予想」を売る伝統芸

おじいさんたちに混じり「大工見習い」として働く31歳女性「毎日幸せだと思って生きている」

「どう乗り越えてやろうかワクワクした」危機を楽しむ強さでコロナに打ち勝つ

大学を中退したのは「回転鮨」が原因だった 「出張鮨職人」のイレギュラー人生

「出張鮨」を誰でも楽しめるものに 「スピード命」の型破りな鮨職人