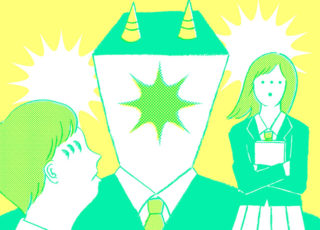もし僕らのことばが生牡蠣であったなら

出せばベストセラーの売れっ子作家といえば村上春樹だが、彼の小説には意外とアンチも多い。その一方で、彼のエッセイは小説ほど人気はないが、文章が見事に磨き上げられていて、個人的にはむしろこちらの方がずっと好きだ。
ジャズからクラシック、ロックにJ-POPまでを縦横に論じた『意味がなければスイングはない』(文春文庫)を読むと、彼が心から上質な音楽を愛していることが伝わってくるし、感覚を正確に言語化する能力の高さに驚かされる。
シングル・モルトを殻に垂らしたい
ウィスキーを飲むためだけにスコットランドとアイルランドを旅する『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)には、彼の小説に出てきそうなクサい比喩が出てくるが、これがルポ風のエッセイになると俄然効果を増してくる。
本のタイトルは、前書きの一節から取られている。日々行き違いの多い生活を送っていると、うんうんと頷いてしまいたくなる。
「もし僕らのことばがウィスキーであったなら、もちろん、これほど苦労することもなかったはずだ。僕は黙ってグラスを差し出し、あなたはそれを受け取って静かに喉に送り込む、それだけですんだはずだ」
挿絵のように入る陽子夫人が撮った写真もまたいい。荒涼とした自然と、そこに生きる羊などの動物や媚びない人々。シンプルな町並みや、美味しそうな料理を前にした夫の姿などが、春樹の文章のように端正に切り取られている。
一度読んで忘れられない個所がある。それは、スコットランドのアイラ島で生牡蠣を食べる場面だ。春樹はボウモア(ウィスキーの銘柄)の蒸溜所のマネージャーに、生牡蠣にシングル・モルトをかけるのがこの島独特の食べ方だ、と教わる。
「僕はそれを実行してみた。レストランで生牡蠣の皿といっしょにダブルのシングル・モルトを注文し、殻の中の牡蠣にとくとくと垂らし、そのまま口に運ぶ。うーん。いや、これがたまらなくうまい。牡蠣の潮くささと、アイラ・ウィスキーのあの個性的な、海霧のような煙っぽさが、口の中でとろりと和合するのだ」
春樹はこの組み合わせを「伝説のトリスタンとイゾルデ」になぞらえ、殻に残った汁とウィスキーの混じったものを飲むこと六回繰り返し、「人生とはかくも単純なことで、かくも美しく輝くものなのだ」と悦に入る。
七つの海を口の中に入れたよう

そんな文章を思い出しながら、東京・高円寺の「かき小屋」にひとり赴くことにした。
いまやご存じの方も増えたと思うが、アイラのモルト・ウィスキーには、ヨードチンキとも正露丸ともいわれるような独特な風味がある。原料のモルト(大⻨⻨芽)を乾燥させるときに燃料にする泥炭(ピート)の香りがウィスキーに移るのだが、これが人によって好き嫌いが大きく出るほど個性的なのだ。
多くの場合、モルト・ウィスキーは複数の種類をブレンドして、香りを複雑にしたり飲みやすくしたりする。これをブレンドせず、ひとつの蒸留所で作ったものだけをボトリングしたのが、シングル・モルト・ウィスキーであり、中には荒々しく尖った個性を誇るものもある。
できれば村上春樹のように、生牡蠣にシングル・モルトを垂らして食べてみたい。しかし、その両方用意してくれる店は、なかなかない。その点「かき小屋」は、600円(税込み)を支払えば飲み物の持ち込みが自由だ。これをうまく利用しない手はない。
高円寺の「カクヤス」には、ややマイルドなボウモアもあったが、どうせならヨード臭の強烈なのでいってみたい。そう考えながら探していると、ラガヴーリンの16年ものがあった。春樹の本の中で、アードベッグに次いで「癖」があると評されているお酒だ。
さっそく生牡蠣の三種盛りを頼むと、宮城のクリーミーパールに、長崎の秋めぐり、島根の春香がセットになってきた。まずはグラスにラガヴーリンをなみなみと注ぐ。ちょっとしたオーセンティックバーならシングルで1000円以上はするが、ここでは遠慮は要らないのでトリプルくらい注いでしまう。
さらに牡蠣の殻をひとつずつ手に取り、グラスからウィスキーを垂らし、その身をぺろりと口の中に吸い込む。ああ、うまい。なるほどなあ。そして、殻の中で混ざった液体をすすってみる。日本の牡蠣とスコットランドのシングル・モルトの異なる海の香りが合わさり、口の中で新たなハーモニーを奏でている。
七つの海を凝縮して口の中に入れたようだ。特に大ぶりな岩牡蠣の春香の貝柱の部分と、ラガヴーリンがお互いを引き立て合い、味わいを深くしていた。ああ、もし僕らのことばが生牡蠣であったなら、あんなことにはならなかったのに――。
もちろん雲丹を乗せて焼いてもおいしい

ひとつ反省点があるとすれば、ラガヴーリンはお酒としては文句なく最高なのだが、クリーミーパールのような日本の牡蠣に合わせるにはちょっと強すぎるかもしれない。春樹はエッセイに、アイラの牡蠣について「ほかの土地で食べる牡蠣とは、ずいぶん味わいが違う。生臭さがなく、こぶりで、潮っぽいのだ」と書いている。
今回の生牡蠣も生臭さは全くないが、アイラの牡蠣の描写と比べると、上品で潮っぽさが控えめなのではないか。もしも真似をしてみようと思われる方がいたら、ややマイルドなボウモアやブナハーブンあたりという選択肢があるかもしれないと思った。
実験を終えてから、鉄板で蒸し焼きにした焼き牡蠣や、牡蠣の雲丹バター焼きなどとも合わせたが、当然ながらこちらもラガヴーリンの堂々たるアテになる。生にこだわらず、火を通した牡蠣でもぜひ味わってみてほしい。ただしお酒が進みすぎるので飲み過ぎには注意だ(ラガヴーリンのアルコール度数は43度)。
それから、勤務先の近くの酒屋で新潟の酒蔵「今代司(いまよつかさ)」が出している牡蠣専用のお酒「IMA for Pairing with OYSTERS」が売っていたので、これも持ち込んで生牡蠣を追加注文した。酸味がよく出ていて、ワインのような味わいだ。
牡蠣と白ワインは相性が悪いと、ぶどうの鉄分で生臭さを増してしまうことがあるが、日本酒ならそういうことは起きそうにない。ただ、このお酒は冷やさなくても、常温くらいの方が旨味がでてよいというのが個人的な好みだ。
帰りがけにコンビニでイワシの缶詰を買って、自宅でラガヴーリンに合わせてみたが、これも意外と合った。これから本格的な海の幸のシーズンになるが、みなさんにもぜひいろんなお酒の組み合わせを試してもらいたい。
この記事をシェアする
「ひとり飯」の記事

「ファミレス」から「ソロレス」へ デニーズに見る孤食の進化

「青い森の幸せな畑」美しい名前の土地で「こだわり料理」を提供するイタリアンレストラン

ひとりの料理、ふたりの笑顔(AIショートノベル 7)

カウンターで食べる「ひとりたこ焼き」がうまい(ひとりで大阪の飲食業界を応援する会 2)

ひとりバーベキューの異常な出来事(AIショートノベル 3)

くじに当たると「めちゃ美味しいすし」が食べられる「立ち飲み鮨 謹賀」(ひとりで大阪の飲食業界を応援する会 1)

「ひとりごはん」の歌を作ったのは松任谷由実? AIが書いた「ひとり飯」コラム

11月23日は「炊飯器の日」 おひとりさま用「弁当箱炊飯器」のプレゼントキャンペーン

「売れ残った海産物を安く買ってほしい」カニカニ詐欺にご注意を