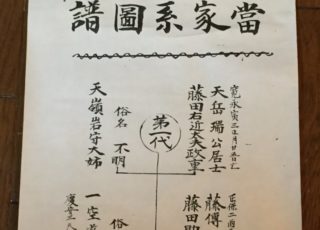不協和音を浴びる愉しみ バルトークの弦楽四重奏曲全曲演奏会をひとり聴きにいく
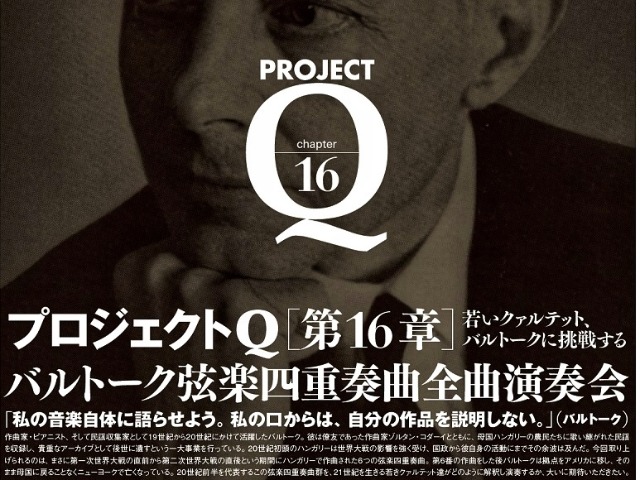
先日、若い音楽家たちによる「バルトーク弦楽四重奏曲全曲演奏会」を聴きにいった(主催:プロジェクトQ実行委員会)。音楽に青春をかける現役の音大生と、卒業したての20代。全6曲を別々の団体が弾いていくという贅沢な企画だ。
とはいえ、このコンサートを楽しめる人はそう多くないのかもしれない。クラシック音楽愛好家の存在がマイナーなのは言うまでもないが、さらに現代音楽の領域とされ、一般的な意味での「不協和音」が連続するバルトーク・ベーラ(1881~1945年)の曲が好きな人はさらに少ない。
したがって誰も一緒に行く人はいないし、無理に来られても苦痛だろうから誘う気も起こらない。でも自分には、これ以上のものが思いつかないくらい期待度の高いイベントなのだ。「ひとりを楽しむ」をコンセプトとするDANROには格好のネタである。
練習を重ねる過程を観客に公開

この演奏会は今年で16年目を迎える「プロジェクトQ」という企画の一環で開かれた。毎年ハイドンやモーツァルトなどのテーマ作曲家を取り上げ、若き弦楽四重奏団(クァルテット)6組が6曲を演奏会で披露する。
この企画が秀逸なのは、厳しい練習を重ねて若者たちが成長する過程を観客に見せるところだ。昨年秋には世界的に著名な音楽家による「公開レッスン(マスタークラス)」が行われ、年明けには「トライアル・コンサート」が3日間にわたって開かれた。
本番当日は午後1時から前半の3曲、午後6時から後半の3曲が披露された。前後半の間は3時間以上あったが、幸い会場の上野学園石橋メモリアルホール(台東区東上野)の近くに素敵なブックカフェがあり、ゆったりとした時間を過ごすことができた。
前半で目を引いたのは、第1番を弾いたアヴァンティ弦楽四重奏団だ(2018年に桐朋学園大の在学生で結成)。演奏機会が少ない初期の作品だが、黒光りする木工品のように隅々まで丁寧に磨き上げた好演だった。第2ヴァイオリンの菊野凛太郎さんの低音が「これがバルトークだ」という感じでよかった。
バルトークらしさといえば、第2番のウナ・クァルテット(2016年に東京藝大のメンバーで結成)もとてもよかった。ヴィオラの野澤匠さんが没頭して弾くパッセージに、ハンガリーやルーマニアの民謡を収集して消化したバルトークっぽい土の香りのする渋さがよく現れていた。
「音楽への共感」が聴衆を感動させる

前半は2人のメガネ男子が印象的だったが、後半は驚くことに12人全員が女性。しかし決して力負けしておらず、特にタレイア・クァルテット(2014年に東京藝大の在学生で結成)の第5番は、これまで聴いてきた中で最も迫力ある演奏のひとつだった。集中度が非常に高く、リスクを取って果敢に表現するスリリングな個所もあって、演奏後はブラボーの声が飛んでいた。
各楽章の冒頭に「Mesto(悲しげに)」と記された晩年の第6番を弾いたクァルテット・ポワリエ(2018年に桐朋学園大の在学生と卒業生で結成)も素晴らしかった。この手の音楽を作り上げることは若い演奏家にはかなり難しかったと思うが、作曲家の意図を高いレベルで理解していることが感じられた。
バルトークの弦楽四重奏曲はいずれも超絶技巧が求められる難曲で、それを弾き果せるだけですごいことだ。その一方で、言うまでもないことだが、技術的にうまいだけでは人を感動させることは難しい。特に再現芸術であるクラシック音楽は「自分がどんな音楽をやっているのか」ということへの理解の深さが、演奏に大きく現れてしまう。
これは大人の世界でも同じだが、自分が携わる仕事の意味を理解して本業を「使命」として全うしようとする人と、単なる稼ぎの一手段としてしか考えない人では、どうしても仕事の質に差が出てしまう。
もちろん意識が高いだけではダメだし、好きじゃなくても得意なことの方が無理なくできるという考えもある。それでも「きっとこの人たちはバルトークに共感していて、演奏できることに喜びを感じているんだな」ということが伝わる場面に触れると、深いところで心が満たされ、生きていればいいこともあるかと思わせてもらえる。
都会に隠れる「凶暴な野生」に気づく
さて、これを読んでバルトークの弦楽四重奏曲を聴いてくれる人がいるかもしれないので、先回りして釘を刺しておきたい。それは「不協和音」は、人間にとって決して無駄なものではなく、世界を知るために必要な芸術ということだ。
世の中には、不協和音を一切認めない人たちがいる。音楽は「音を楽しむもの」だから、わざわざ不快になる必要がないという主張だ。しかし、音楽が複雑な世界を表現しようとすれば自ずと響きは複雑になり、いわゆるドミソ的音楽から外れていくのは自然である。
たとえば、恋愛によって引き起こされる感情は、ある方向からは甘美だけれど、別方向からは一種の精神的ストレスに違いない。不協和音をすべて不快なものとしか捉えないのは、恋愛の心理的葛藤なしに欲望を単純にかなえようとするのと同じことだ。
太古の音楽には、いまで言う分かりやすいハーモニーがあったわけではない。「協和音」の世界しか受け付けられない人は、除菌された近代西洋音楽の影響を受けた教育やメディアによって、ある種の「洗脳」を受けてきたのかもしれないのである。
また、この6曲が2つの世界大戦の間にハンガリーで書かれたことや、バルトークが森に迷った猫のかすかな鳴き声を聴き取って救いにいったエピソードなどを知ると、彼の不協和音により共感できると思う。
一日中バルトーク漬けになって暗い夜道を帰りながら、アスファルトで覆われた文明社会も、ひと皮剝けばその下には凶暴な野生が眠っているような気がしてきた。そしてふと、クロード・レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』に出てきた「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう」という言葉を思い出した。
この記事をシェアする
「ひとり趣味」の記事

「サブカル沼」に沈んだ青春が、クリエイターをつくる

ひとり音楽と猫と山下達郎(AIショートノベル 8)

宇宙人に遭遇したときに歌いたい「この素晴らしき世界」

ひとり時間に「手紙」を書くと、ゆったりした時間が戻ってくる

江戸城の「富士見櫓」をめぐるミステリー。江戸時代のものか、復元か?(ふらり城あるき 11)

なぜ人は「鼻歌」を口ずさむのか? スピッツの「ロビンソン」をきっかけに考えてみた(いつも心にぼっち曲 7)

田んぼの真ん中にバリ風の「ヨガ道場」を建てた女性 なぜこんなものを作ったんですか?

「僕はどれだけ拍手に元気づけられてきたんだろう」コロナ禍で40周年をむかえたスターダスト☆レビュー

SNS疲れで眠れない夜、谷山浩子の「銀河通信」が心を軽くしてくれる(いつも心にぼっち曲)