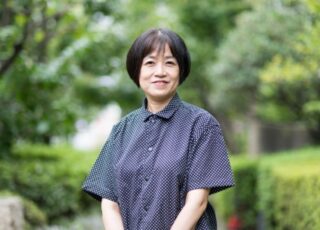安田純平さんが語る人質の孤独。それでもひとり紛争地から伝えたいこと(前編)

内戦中のシリアで3年4カ月にわたって武装勢力に身柄を拘束され、2018年10月に解放されたジャーナリストの安田純平さん。帰国直後の慌ただしさが一段落したころ、DANROのインタビューに応じ、現在の心境を語りました。
安田さんは、黒い帽子にマスク姿で、指定のインタビュー場所に現れました。「家族が心配するから」あまり出歩かないようにしているとのこと。メディアのインタビューを受ける際にも遠出ができず、「近所のカラオケボックスに1日3回入ったことがある」といいます。
フリーランスのジャーナリストとして、単身で主に中東の紛争地の取材を重ねて来た安田さん。一人であるが故に避けられないリスクがあり、一人で拘束されていたときは孤独感が募ったといいます。それでも一人で行動しながら伝えたいこととは、どんなことでしょうか。インタビューの前編です。(取材・吉野太一郎/亀松太郎)
【インタビュー後編】安田純平さん「事実関係の説明ってすごく地味。でも…」ネット時代のリスクと情報発信

「自由を奪われた状態」は精神的にきつい
――体調はいかがですか?
安田:帰国した頃は、ヘルニアがかなりひどかったんですけど、少し落ち着いてきました。かなり筋肉が落ちてしまっているので、非常に疲れやすくて。少しずつ運動とかして戻すしかないんですけど。
また、おそらく拘束中に現地で飲んだ生水の影響で、ピロリ菌による胃潰瘍と十二指腸潰瘍がありました。帰国して除菌したので、少しは収まったかなと思います。
――長いことずっと拘束されていて筋肉が弱ったんですか?
安田:身動きが完全にできなかった時期が約2カ月ありました。別の施設に移されて半年間は、部屋の中を歩く以外は運動禁止だったので、上半身が全然使えませんでした。最後の1カ月はまた、身動きがほとんどできない場所だったので、せっかく戻った筋肉がまた落ちてしまった。筋肉が落ちた状態で腰に負担がかかって、ヘルニアになったという気がしています。
――海外で極限状態に置かれていたので、食事や体調、精神面など環境の変化が体にこたえたのでは?
安田:そうですね。常時、頭皮がピリピリしていて、頭に血が上っているような状態でした。神経にかなり来ていたんだと思いますね。身動きができるようになっても、いつ終わるか分からない「自由を奪われた状態」というのは精神的にきついので。
「どんな状況であっても、そこで見たものはひとつの情報」
――安田さんは信濃毎日新聞を退職してから特定のメディアに属さず、ずっとフリーランスで、主に中東方面を長く取材してきました。一人で戦地を取材するのはかなり困難が伴うと思いますが、なぜそうしようと思ったのですか?
安田:資金面やサポート態勢でメディアに属した方が有利な面もあるんですけど、雇用の関係になると、組織の事情がどうしても優先されます。それに、今回のようなことが起きたときに組織に影響が出るので、一人の方が身軽というのがありますね。
また、フリーランスのグループに属する方法もあるんですけど、所属しなくてもそういう人たちと情報交換はできますし、一人の方が気が楽だというか。
――信濃毎日に勤め始めた時点からフリーになることを念頭に置いていたのでしょうか?
安田:必ずしもそうではありません。2003年にイラク戦争が始まるとき、あの規模の戦争を現場で見る機会はなかなかないから、今のうちに見ておきたいというのがありました。
――信濃毎日時代から休暇を取って海外に行っておられましたね。
安田:信濃毎日新聞は地方紙なので、海外に限らず、会社の出張でどこかに行くのがそもそも難しい。自分の時間と金でどこかに行って、それを記事に出来ればそれでいいと思っていたんですけど、休みを使って行って、確実に帰ろうとすると、現地にはどうしても数日しかいられない。開戦の時点で現地にいるのは無理だと思ったんです。
自分の取材のスタイルを考えると、時間をかけてじっくりやりたい。それはやっぱりフリーランスの方がやりやすいので、そのスタイルでこの年齢まできています。

――イラク戦争の開戦直前には、安田さんも含めて、若い人が「人間の盾」という名目でたくさん現地に入っていました。
安田:当時はサダム・フセイン政権がそういう種類のビザを発行していました。自分のような取材目的で入る人もたくさんいました。現場に入りやすかったんです。
ただ、戦争は止まらなかったし、(民間人を入国させて米英の侵攻を防ぐという意図は)基本的には機能しなかったわけです。戦争で攻め込まれる側の国がまたこれをやるかというと、もうないかもしれないですね。
――フリーで戦地を取材する場合、自分の身は自分で守ることが前提になるという意味で、今回の拘束されたことをどう考えますか?
安田:うーん…当初の目的を果たしたかという意味では失敗ですね。結局、政府を当事者にさせてしまったので。
ただ、内戦中のシリアで反政府側の地域に入るには、どこかの現地組織の手引きがないとまず入れない。でも、どこかの組織の受け入れで入った場合、拘束施設や拷問の様子、人身売買されてきた人が入ってきた様子とか、まず見られないと思うんですよ。
少なくとも記者の仕事をしているのであれば、どんな状況であっても、そこで見たものはひとつの情報です。そういう情報の中から価値のあるものを見いだせる人もいますし、次にも生きてくる。失敗そのものが貴重な情報ですよね。
「日本の場合、社会の反応もリスク。かなり厳しい」
――たとえば北朝鮮に取材で行く場合、記者としての入国自体、簡単ではないし、取材にも様々な制限がある。そこを突破するのは非常にリスクが高い。国交がないから、いざというとき誰も助けてくれる人がいないので、結構心細いものがあります。おそらくシリアも似たようなものと想像します。そういう中でどれだけ危険な場所に突っ込んで行くべきなのでしょうか。
安田:おっしゃったように、やりたいものと、それをやるときのリスクの比較しかないですよね。自分自身の命のリスクと、それが起きた時の社会的なリスク。そのあたりも含めて、てんびんにかけるしかないですよね。
――安田さんの場合は「行ける」という判断をした。
安田:そうですね。ただ、社会の反応というのもリスクです。そこを考えると、日本社会というのはかなり厳しい。
新潟のフリーカメラマンの杉本祐一さんは、「シリアに行く」と行っただけでパスポートを没収されました。自分の身に起きること自体は、気にしなければ済むかもしれないけど、パスポート没収といった反応をされるとなると、そうもいかなくなってしまう。
ヨーロッパの記者はたくさん人質になっていますが、それでも現地に入る人はたくさんいる。自分自身に起きるリスクは大きくても、社会的なリスクは日本人ほど感じてないのかなと思うんですけどね。
現に被害者がたくさん出ている場所であれば、取材に入る側もリスクは大きくなりますが、そういう場所だからこそ、現場を見る必要性も大きくなる。リスクだけを考えていたら、何もしない方がいい。それでも行くべきか。シリアの内戦は、そうして外部の目が入らない間にどんどんひどくなって来た現状があると思います。

――よく言われることですが、日本の社会は失敗に対して非常に厳しい社会です。一度でも失敗すると、厳しく叩いて立ち上がれなくしてしまう。今回のことも、安田さんを絶対悪のように批判する人が多い。一方でヨーロッパの記者が社会的リスクを恐れないという背景には、それぞれの責任は個人の問題だという「個人主義」的な風潮もあるのかもしれませんね。
安田:個人主義というか、個人を支える社会ですよね。お互いが尊重されている。誰も行かない場所に行くというのは、当然リスクはあるわけですし、誰もやったことのないことは、やってみないと分からない。そこにいろんな人が挑戦する。そういう裾野があって、初めて、新しいものがどこかで見つかってくる。失敗に寛容でない社会は、なかなか発展していくチャンスがないと思うんですけどね。
「捕まっている状態で、ただひたすら悔やむだけ」
――現地で拘束されていた間は3年以上、一人で、孤独でした。日々どんなことを考えていたのですか?
安田:当然、「必ず帰れるものだ」と思っておくしかありません。。「帰れたら日本で何をしたいか」というのもありますし、「捕まえた奴らの正体を暴きたい」とずっと考えていました。
あとは、新しい情報がなかなかないので、どうしても過去を振り返る作業になってしまう。どうしても現状を否定したくなって、そこに至る過去まで否定せざるをえなくなる。これまで充実した人生を送っている人であれば、過去を振り返っても辛くないかもしれないけど、自分の場合は「もっと違う人生があったかもしれない」とか考えましたね。
――「信濃毎日を辞めなければ」とか。

安田:そういうのもありますね。新聞記者になったことも含めて、過去のいろんな場面で、すべての選択肢を「違う道があったかもしれない」と。
――死ぬ間際に走馬灯のように過去の出来事がよみがえる、という話を聞きますが。
安田:生きて帰れるかどうか保証がないわけで、まさに走馬燈です。拘束されていなければ、おそらく将来死ぬとき、同じ走馬燈を見ることになるわけですよね。それを見ても、もう取り返しがつかない。捕まっている状態で過去を振り返る作業というのは、前向きなものが何もないので、ただひたすら悔やむだけ。これは非常に辛い作業です。だから「必ず生きて帰れる」ということを前提にしないと、否定するだけになってしまう。「絶対帰れる」と考えるしかないですよね。
過激派組織「イスラム国」(IS)に捕まっていた場合は、そうは思えないでしょうから。(ISの人質になって殺害された)後藤健二さんは相当辛かったと思うんですよね。それでも最後まで希望を持っていたという証言がありましたから、本当に強い人だったと思いますよ。私の場合は、ISがあの地域で活動していなかった。それだけでもだいぶ違いました。
――3年4カ月拘束されている中で、直接的に死の恐怖を感じるような場面はあったのですか?
安田:それはないですね。
――拘束されている間、この状態が永遠に続くかもしれないと考えたりはしましたか?
安田:そういうことを考えることもありました。途中から「身動きしてはいけないルール」が始まって、それをクリアしないと帰されない。それは実際には不可能でしたから、それが永遠に続くのかという恐怖感はありましたよね。
注:安田さんを拘束していた武装勢力は、拘束の終盤、安田さんが部屋で何か物音を立てると、扇風機を消したり電気を点滅させたり、他の囚人を見せしめに拷問したりといった嫌がらせをした。安田さんは「身動きをしてはいけないゲーム」で、クリアすれば解放されると解釈していた。

安田:後藤さんの事件も日本で見ていましたけど、拘束されて人質になることが、どれだけ辛いものなのか、自分が同じような状態になって初めて理解できた。自由を奪われる恐怖というのは、味わってみないとわからない部分があって、自分も今回、想像していた以上に非常にきついものだと実感しました。無期懲役の恐怖というのは非常に大きいですよね。
――3年4カ月というタイミングで解放されたことについて、何か思い当たる節はあるのでしょうか?
安田:きりがないとは考えていたでしょうね。ただ、帰すんだったらもっと早く帰せたでしょう。「反政府側が追い詰められてきていた」とも言われていますけど、大きな施設の中に入れているだけなんで、日本人1人捕まえていることなんか全然負担じゃないと思いますよ。
――自分を理解してくれる人は施設にいなかったのですか?
安田:同情的な人はいました。セキュリティー(公安部門)の連中は完全に私をスパイ扱いしていましたが、現場の看守連中は同情的でした。ただ、食べ物をちょっと多めに持ってくるとか、「大丈夫だ」というようなサインを送ってくるとか、その程度の話。解放につながるような同情はなかったですね。結局、私の処遇はトップが決めるので。
組織には、他人の人生なんかどうでもいいという異常な感覚の連中と、そうでないのが混ざっている状態なのだと思います。私の処遇がきっかけで、組織の中に波が起きて、組織が割れてしまう可能性もあるわけですよ。そういう事情もあって、初めから「殺す」ということは考えてなかったと思うんですね。
「うちの組織は身代金を取れなければ殺さないで帰すから」とはっきりと言われました。でも、そういうことを言っていることがバレると、看守から外されちゃうんですよ。だから初期の同情的なメンバーはほとんど外されて、後の方はとにかく「どうすれば苦しめることができるか」ということを考える連中ばっかりになっちゃいましたね。
「もっと冷静に対応できていれば、もっと早く解放されていたかも」
――スパイ容疑はずっと最後までかかっていたのですか?
安田:最初のスパイ容疑とは別に、拘束中に彼らの話を聞いてスパイ行為をしているということにされました。周りでアラブ人の囚人が普通に聞いている話を、彼らほどアラビア語が分からない外国人の自分が聞いても何の価値もない。聞かれたくなければほかの囚人から離せばいいのにそうしないわけで、単なる嫌がらせですよね。
――外国で言葉も不自由な部分が多い中で、ちょっとしたコミュニケーションのすれ違いで致命的なことがおきかねない状況だったのではないですか?
安田:自分を拘束した組織は、ある程度の規模があったので、突発的な判断で殺すということはあまりないと思うんです。殺すときは組織としての判断になりますから。
ただ、「スパイ行為をしている」と、相手が勝手に誤解し始めることはあるので、「もっと冷静に対応できていれば、もっと早く解放されていたかもしれない」と考えざるを得ないところはありますよね。看守と余計な話をしてしまったりとか。
あまりに理不尽な言いがかりをつけられて、それがいつまでも続きそうだと思ったときは何度もドアを蹴っ飛ばしたりもしました。もっと冷静な人であればもっと早く解放されたと思うんですよね。そういう意味ではいろんなミスがあったと思っています。
――拘束されているときもある種、記者として今の自分の状況を記録して伝えようという気持ちはあったのですか?

安田:もちろんそうです。空爆の音が聞こえた時間も全部記録しています。極めて特殊な状況ですから、 生きて帰れた場合、記録できるものは全て記録しておくべきだと思っていました。
――それ自体が支えになっていたのでしょうか?
安田:記録するということは持って帰るのが前提ですし、記録したり観察したりというのは前向きな作業なので、それをしなくなると精神的にも肉体的にもかなり落ち込んじゃうと思うんですよね。
ただ、ノートやペンも、(拘束されてから約2年後の)2017年の4月ぐらいにはもらえなくなりました。全部終わったのが2018年の8月いっぱいぐらいまでですから、記録できたのは半分ぐらいです。
――形になりそうなものはあるんですか?
安田:書籍にするという話はたくさんいただいています。
【インタビュー後編】安田純平さん「事実関係の説明ってすごく地味。でも…」ネット時代のリスクと情報発信
この記事をシェアする
「ひとり仕事」の記事

「10歳のころの自分が笑えるネタか」さかな芸人ハットリさんが大切にしていること

「目撃すれば幸せになれる」とウワサが広がる「自転車で文字を売る男」

個室のない私が「畳半分のワークスペース」を手に入れるまで

ひとりで山を歩き「食べられる野草」を探す 「山野草ガイド」を作る地域おこし協力隊員

「当たればお立ち台、はずれたら死刑台」競馬場で「予想」を売る伝統芸

おじいさんたちに混じり「大工見習い」として働く31歳女性「毎日幸せだと思って生きている」

「どう乗り越えてやろうかワクワクした」危機を楽しむ強さでコロナに打ち勝つ

大学を中退したのは「回転鮨」が原因だった 「出張鮨職人」のイレギュラー人生

「出張鮨」を誰でも楽しめるものに 「スピード命」の型破りな鮨職人