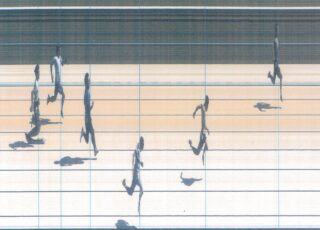脳のないナマコから学べることってあるの⁉ 生物学者に聞く

生き物なのに、目もなければ鼻もない。それどころか、心臓や脳みそもない。群れを作らず、海のなかでただ砂を食べているーー。それが、ナマコです。
脳がないということは当然、悩みもないということ。それってある意味、究極の生き方では? もしかして、ナマコから学べることがあるのでは? そう思いたって、生物学者・本川達雄さん(70)に会いにいきました。
本川さんは、ナマコ研究の第一人者。東京工業大学の名誉教授で、ベストセラーとなった『ゾウの時間 ネズミの時間』の著者としても知られています。
ーーナマコには脳がないということですが、「脳のない生物」がいること自体、感覚的に理解できないというか、うまく飲み込めません。
本川:脳というのは、神経細胞が集まった塊です。目からの入力に対して膨らんでいる部分があったり、鼻からの情報に対して膨らんでいる部分があったりして、感覚器官につながっているのです。ナマコのように感覚器官のない生物には、それがいらないわけです。

ーーまさに「無神経」ですか。
本川:ナマコにも神経はあるんです。ただ、それを処理する、いわば大規模なコンピューターがないんですね。
ーーそうだとすると、結局、ナマコは「進化」したのですか? それとも「退化」したのですか?
本川:退化といえば退化なんですが、ナマコやウニ、ヒトデなどの『棘皮(きょくひ)動物』は、動かなくていい生活をするようになったんです。砂についた栄養をとったり、流れてくる微生物を身体のなかの『網』で濾(こ)して食べたり。それにともなって、脳なんか、なくなっちゃった。
ーーなんとも不思議な生物ですね。
本川:それでもホヤやナマコ、ヒトデなどは、昆虫なんかと比べると、僕らヒトと非常に近い生物です。ヒトとナマコはいわば同じ系統でありながら、神経を発達させるかさせないかで両極端にいっちゃったんですね。
素粒子と文学の「真ん中あたり」で動物学に

ーー本川さんは、なぜナマコを研究することになったのでしょうか?
本川:沖縄が本土復帰してから7年目に、琉球大学の研究施設に行ったら、その近くの海にナマコがたくさんいたんです。なぜ沖縄に行ったかというと、東大での助手時代、「若い研究者を沖縄に送ってほしい」という話があったからです。
ーー自ら志願したんですか?
本川:学生運動のとき、あれだけ沖縄の本土復帰を訴えていた人たちが、誰も手を挙げないんです。学生運動を引っぱっていた人たちは頭が良かったから、変わり身も早かった。それに腹が立って、僕が手を挙げたんです。行ってみたら、機材はない、学生がいない、研究用のマウスを手配する流通もない状態で、大変でした。
ーー「海の生き物が好きだったから」という理由ではないんですか?
本川:いえ、動物は嫌いなんです。
ーーでは、なぜ、そちらの道に進んだのでしょうか。
本川:僕が学生だったころ、理学部では素粒子物理学が華やかでした。究極の粒子である素粒子がわかれば、世界がわかると考えていたんです。一方、文学部や心理学部では、脳や心がわかればすべてがわかると思っている。僕には、そのどちらもが偏った見方に思えた。だったら、その真ん中くらいをいこうと。それは動物学じゃないかと考えた。だから動物は嫌いだったけど、そこに進もうと決めたんです。

ーー「素粒子」でも「脳や心」でもないところから、世界を解明しようとした?
本川:解明しようなんて思いません。世の中を解明することなんてできませんから。ただ、理解したかったんです。理解というのは、人間の理性が腑に落ちて納得すること。それが真理かどうかは、わからないんです。科学の世界には科学の世界の「真理」がありますが、それは「こういう風に解釈すれば納得できる」という納得の部分をいっているだけで、現象学の話なんですね。
ーー難しい話ですが、少しわかった気がします。
本川:それこそ、ナマコなんて、我々とは世界が違うわけです。だから多くの人は、異質なものとして排除してしまう。でも、違う世界を理解しようとする姿勢こそが大切です。科学では共通性ばかりをいうけども、むしろ共通でないところが大事。ナマコの研究でも、ナマコという不可解なものを理解可能なものにできるかが勝負だった。
ーーわからないからこそ、向き合うということですね。
本川:いまは皆、お気に入りのものだけを周りに集めて、自分の世界を作っている。でも、それで世界が広がったように感じるのは、危ういと思います。自分とは違うものをいかに理解して付き合っていくかというのをやらないと、世界は広がっていきません。
この記事をシェアする
「ひとり仕事」の記事

「10歳のころの自分が笑えるネタか」さかな芸人ハットリさんが大切にしていること

「目撃すれば幸せになれる」とウワサが広がる「自転車で文字を売る男」

個室のない私が「畳半分のワークスペース」を手に入れるまで

ひとりで山を歩き「食べられる野草」を探す 「山野草ガイド」を作る地域おこし協力隊員

「当たればお立ち台、はずれたら死刑台」競馬場で「予想」を売る伝統芸

おじいさんたちに混じり「大工見習い」として働く31歳女性「毎日幸せだと思って生きている」

「どう乗り越えてやろうかワクワクした」危機を楽しむ強さでコロナに打ち勝つ

大学を中退したのは「回転鮨」が原因だった 「出張鮨職人」のイレギュラー人生

「出張鮨」を誰でも楽しめるものに 「スピード命」の型破りな鮨職人