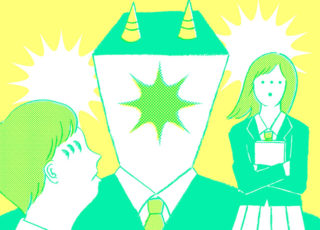「撮りたいのはインコの生涯」 10年間、一羽のインコ「おとちゃん」を撮り続ける写真家

「インコのおとちゃんをかわいく撮ろうと思ったことは一度もないです。撮りたいのは、インコの一生。孤高に生きる、その姿なんです」
大阪市平野区にアトリエを構える写真家の村東剛さん(52歳)は、そう語ります。
村東さんの名が巷に一躍知れ渡ったのは、2014年に上梓した写真集「インコのおとちゃん」(パイインターナショナル)がきっかけでした。2007年に村東さん宅へとやってきたコザクラインコの「おとちゃん」を撮影したこの写真集は、四刷を数えるベストセラーに。
以来、写真集やカレンダーを続々と発行し、2019年2月には小学館より「インコのおとちゃん それからこれから」を出版することになりました。

しかし村東さんは、決して動物写真家ではありません。日頃は雑誌や広告で主に人物を撮影しています。27年のキャリアのうち、動物は、飼うのも撮り続けるのも「おとちゃん」ただ一羽のみ。
目を見張るのは、表情の豊かさ。笑顔を見せることもあれば、人間には見えない世界を注視しているかのような神秘的な目をすることも。「インコって、こんなにもたくさんの顔があるのか」と驚かされるとともに、確かにかわいいだけでは留まらない、インコの半生が浮かびあがってきます。
10年以上、一羽のインコの姿をひたすら被写体として撮り続け、インコとともに歩む人生を選んだ村東さん。「おとちゃん」との暮らしのなかで見えてきたものは、いったいなんだったのでしょう。

「運命的なものを感じた」というインコとの出会い
――インコの「おとちゃん」を飼いはじめたのは、なぜですか。
村東:うちの夫婦は子どもがいないんです。それで寂しかったのもあり、妻と「動物を飼おうか」という話になりました。犬や猫を飼うことも考えたのですが、「ラブバード」と呼ばれる鳥がいることを知ったんです。それがコザクラインコでした。
ラブってところが気に入ってさっそく小鳥屋さんへ行ったら、一歳になるコザクラインコのオスがいたんです。妻も僕も、なぜかその子にだけ運命的な出会いを感じましてね。「この子、ええなあ」って妻と顔を見合わせて、飼うことがあっさりと決まりました。不思議なもので、そのときすでにペットという感覚ではなかったんです。
――ペットではないとなると、どういう感覚だったのでしょう。
村東:もともと子どものかわりというか、新しい家族を迎えるつもりで小鳥を買いに行ったんです。でも初めての出会いで、家族というより、人生をともにする同志と巡りあえた気がしました。「この子となら、わかりあえる。やっていける」って。まだ一歳のひなに対して大げさなんですが、ずっと探していた友人と出会えたような、そんな感覚をおぼえたんです。飼う前から、早くも特別な存在でした。

――なぜ「おとちゃん」という名前をつけたのですか。
村東:当時テレビで『あかんたれ』(1976年制作)という明治中期の大阪・船場の呉服問屋を描いたドラマの再放送をやっていまして、好きでよく観ていたんです。この『あかんたれ』に、いじめられている丁稚を助ける「音松」という男が出ており、その賢さにいつも感心していたんです。そして「音松のような、賢明で情にあつい鳥になってほしい」という想いから、「おとちゃん」と名づけました。
「おとちゃんは自分の一生を懸けるに値する被写体だ」
――おとちゃんの写真を撮るようになったのは、なぜですか。
村東:飼いはじめて、表情やポーズが豊富なことに驚いたんです。それまで鳥って無表情だと思っていたから。しかし、喜びの表情もあれば、憂いを感じることもある。小鳥のイメージが完全に覆りました。そのとき、僕の“写真家魂”に火が点いたんです。「おとちゃんは自分の一生を懸けるに値する被写体だ」と感じました。


「おとちゃんをかわいく撮ろうと思ったことは一度もない」
――確かに、おとちゃんの写真を見ていると、かわいいだけではないですね。「鳥の心」が伝わってくる気がします。そして、それを撮る村東さんの気迫も感じます。
村東:おとちゃんをかわいく撮ろうと思ったことは、一度もないんです。もともと仕事で撮るポートレートも、笑顔だけを追うタイプの写真家ではなかったですし。かわいさよりも、撮りたいのは、かっこよく言うと「インコの生き様」ですね。わがままで、強気で、自分勝手ですぐ怒る。でも甘えん坊で、寂しがり屋さんで、それでいて凛々しくて、孤高を感じることもある。そんな一羽のインコにある多様な面をカメラで追ってみたいと考えました。
――インコの多様な面は、どういうときに感じられますか。
村東:たとえばテーブルの上にレシートを置いておくでしょう。するとそれを口にくわえて、自分の尾羽に挿して、すました表情をしている。きっと、おしゃれをしているんだと思うんです。そういう姿を見ると、気高さも感じるし、反面、おかしさもあって、いっそう愛おしくなりますね。

おとちゃんを飼うようになり「思いやる」ことの大切さを知った
――小鳥を飼うことで自分たちが変化した点はありますか。
村東:室温の管理は徹底的にやらなくてはならないですし、誰かが必ず家にいなくてはいけない。一度夫婦で二泊の東京出張をしたとき、帰ってきてみたら、自分の毛を自分で抜いて丸はげになっていたんです。体重も3グラムも落ちていた。もともと49グラムからのマイナス3グラムですから、相当な痩せ方です。寂しかったんでしょうね。鳥と生きるということは、すなわち「思いやる」ということなんだと痛感しました。
あれから夫婦ふたりで家を空けることはありません。そんなふうに、おとちゃんのおかげで考え方や人生観が変わった部分は多々あります。たまに「もしも、おとちゃんがいなかったら、離婚してたんじゃないか」って思うこともあるんです。
――そう聞くと、この質問はひじょうにしづらいのですが、確実にインコの方は寿命が短いですよね。いつか迎える「その日」を、どのようにとらえておられますか。
村東:おとちゃんは現在、人間の年齢で換算すると、およそ60歳です。僕よりもずっと先輩になりました。白内障が進んで、飛ぶときも「おそるおそる」という感じです。なので覚悟はしています。起きる出来事のすべてを受け入れるのが、写真家として「インコの一生を追う」ということだと思うし、おとちゃんは、僕のアイデンティティそのものですから。
「インコ」に関するおすすめ記事
この記事をシェアする
「ひとり趣味」の記事

「サブカル沼」に沈んだ青春が、クリエイターをつくる

ひとり音楽と猫と山下達郎(AIショートノベル 8)

宇宙人に遭遇したときに歌いたい「この素晴らしき世界」

ひとり時間に「手紙」を書くと、ゆったりした時間が戻ってくる

江戸城の「富士見櫓」をめぐるミステリー。江戸時代のものか、復元か?(ふらり城あるき 11)

なぜ人は「鼻歌」を口ずさむのか? スピッツの「ロビンソン」をきっかけに考えてみた(いつも心にぼっち曲 7)

田んぼの真ん中にバリ風の「ヨガ道場」を建てた女性 なぜこんなものを作ったんですか?

「僕はどれだけ拍手に元気づけられてきたんだろう」コロナ禍で40周年をむかえたスターダスト☆レビュー

SNS疲れで眠れない夜、谷山浩子の「銀河通信」が心を軽くしてくれる(いつも心にぼっち曲)