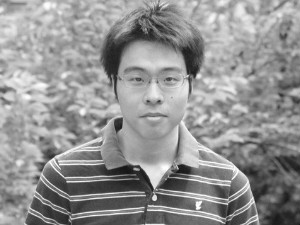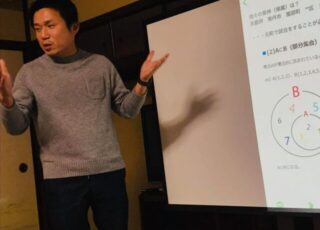「認知症になっても終わりではない。母はやっぱり母」認知症の母を撮影する日々

『ぼけますから、よろしくお願いします。』。そんなタイトルの「認知症」を題材としたドキュメンタリー映画が11月3日から公開されています。もともとテレビ番組として放送され、大きな反響を呼んだ本作。追加取材と再編集が行われ、劇場用映画として公開されました。
監督は、北朝鮮拉致問題やネットカフェ難民などさまざまな社会問題に切り込んできたテレビディレクターの信友直子さん(56)。東京で40年近く暮らす信友さんが、広島で生きる95歳の父と87歳の母の「日常」をみつめます。認知症であることを突きつけられて苦悩する母。95歳にして初めて家事に挑戦する父。そして両親から離れて暮らす信友さん……。
娘として、テレビディレクターとして、信友さんはどのように両親と対峙したのでしょうか。

認知症になっても「なんとかなる」と思える作品を
――両親を題材にしようと思ったきっかけを教えて下さい。
信友:2000年に自分のホームビデオを買ったんですね。いわゆる家庭用のホームビデオ。翌年の正月に帰省したときに、プライベートでなんとなく撮り始めました。最初は、お父さんが息子の運動会を撮るような感じでした。
――「老々介護」を中心に据えると、暗いテイストの作品になってもおかしくはありませんけど、そうなってはいませんね。
信友:両親も私も楽観的なので、あまりくよくよは考えなくて(笑)。それ以前に、私はシリアスで救いのないドキュメンタリーは作らないようにしています。救いがないと、視聴者の方も辛いですし。見た方が笑えて、家族や自分が認知症になっても「なんとかなる」と思えるような作品を目指していたので。
――本作のプロデューサー、大島新さんの「ディレクターとして両親に冷静な眼差しを向けている」という言葉が印象的でした。
信友:一歩引いてみたほうが、気が楽になるんですよ。まっすぐに向き合いすぎると、母の行動の一つひとつに左右されて疲れるし、あまり状況として良くはないんです。チャップリンの名言で、「人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ」という言葉がありますね。それが本質だと思うんです。必死になると、鬱っぽくなるなと。ちょっと引いた視点で見ると、ちょっとぼけたおばあちゃんと、耳の遠いおじいちゃんの日常で、なんかかわいく見えてきたりもするんです。

母の認知症から見えた、新たな父の姿
――認知症を題材とした映画『ペコロスの母に会いに行く』(森崎東監督)の中で、「ぼけるとも悪か事ばかりじゃなかかもしれん」という台詞がありますが、それを思い出しました。
信友:そう思います。ぼけないに越したことはありませんけど、私の場合、母がぼけたことで、父とたくさん話すようになったのは「良いこと」でした。父が口下手だったのもありますけど、家庭では、私は母とばかり話していて、父はふたりが話している横で、だまって新聞を読んでいるような感じだったんです。父のことを好きなのかどうかも、よくわからなくて (笑)。
でも、母が認知症になってからの5、6年で、父とたくさん話すようになって。そうしたら、父は案外いい男だなと思うようになったんです。妻が認知症になって、あそこまでかいがいしく面倒を見る夫ってなかなかいないんじゃないか、と。これまで全く家事をやってなかったのに、掃除も料理も、さらには繕い物もできるようになって。
それまでは父と母がそんなに仲良くも見えなかったのに、母が父に甘える姿とか、父もそれに応えるような姿もよく見られるようになって。新たな両親の姿が見えてきたのがよかったと思います。
――両親を撮影する過程で、ご自身が予想もつかなかったことも多かったと思うのですが。
信友:父が母に対して、激しく怒った時はびっくりしましたね。今までいろんな家を取材してきましたけど、こんな大バトルは一回もなかったので、「いい絵だ」と直感で思いました。ご飯を作ったり、洗濯をする中で、何か起きたらカメラを回すという感じなんですけど、日常においては「娘としての目」と「ディレクターとしての目」が、いったりきたりなんです。娘として人に見せるのは恥ずかしいと思うような行動も、ディレクターとしてはとてもいいと思ったり。
――信友監督は、森永製菓に就職したのちにテレビ業界に入りました。当時としては異例な道を歩んだのだと思いますが、同世代の人と比較して、自分の生き方を考えたことはありますか。
信友:私は「自分の表現をしたい」という思いが昔からあって、人と比べてもそれは顕著だったんです。就職においては、自己表現をするのに最適な場を探したという感じでした。当時はコピーライターになりたくて、森永製菓の広告部に入ったんですけど、企業製品のPRがメインなので、規制とかも多かったんです。仕事でコマーシャルの撮影現場に行く機会があり、そこで、カメラを回すほうが断然おもしろそうだと。そうしてテレビの制作会社に転職して、現在の私への大きな一歩となりました。
給料とか世間体がどうかということよりも、自分がやりたいことに向かって走っていった感じです。恋愛とかも人並みにしましたけど、向こうの要求と私のやりたいことが合わなかったりして、結婚には至らなくて……。同級生のライフステージの変化、たとえば、子どもが生まれて、小学校に入学して、というプロセスを聞いて「人の道を外れているんじゃないか」とコンプレックスを覚えたこともあります。でも、自分の表現への欲求を考えると、それに従って生きざるを得なかったという感じがするんですね。

既成概念からいかに離れるか
――信友監督の、テレビディレクターとしての哲学をお聞かせいただけますか。
信友:私の作品に通底しているのは、もともとあった既成概念を壊して、フラットな状態で見直すということです。たとえば1994年に発表した『NONFIX 青山世多加』ですね。身体障がい者のお笑い芸人、ホーキング青山さんのデビュー前を追った作品です。当時の障がい者のイメージは、聖人君子扱いというか、障がいにもめげずに頑張っている、心のきれいな人たちといったものだったんです。でも、障がい者にもいろんな人がいて。
もちろん優しい人もいますけど、意地悪な人もいますし。彼は性欲も強くて、笑いをまじえたエッチな話もよくしていました。それで、青山さんの「性」の部分も語るようにしたんですけど、それは当時のテレビ番組としては画期的と言われたんです。ただ、思春期の男の子ならば、むしろ「性」に興味がないほうが珍しいですよね。特別扱いせず、清いところ以外にも光を当てるほうが、差別ではないんです。
――そのような既成概念を壊そうという哲学は、『ぼけますから、よろしくお願いします。』でも感じられますね。
信友:認知症って、みんな怖い病気だと思うんですよ。根本的な治療法もないし。でも、気持ちの持ち方によって、認知症を抱えながら楽しく暮らすこともできるんじゃないかと。本作は、そうした仮説を検証するための、ひとつの実験みたいに思っているんです。認知症になっても終わりではないし、母はやっぱり母ですし。
こんなできごとがありました。ヘルパーさんがすごく料理のうまい人で、父が「一回で食べたらもったいない、半分だけ食べて明日も食べよう」と置いておいたら、夜中に母が起きて、全部食べてしまったんです。翌朝、目覚めた父が激怒したんですけど、母は覚えていない。そういうことって面白いですよね。意外に笑いにはできるんです。
認知症になったらいろいろと心配なことは出てきますけど、未来を悲観するんじゃなくて、その状況をいかに楽しむかを考えることが大切だと思います。今を楽しんで、笑って過ごすことを多くの方に勧めたいです。ですから、本作は必ずしも認知症の映画ではなく、ひとつの「生活の知恵」の映画であるとも思っています。

この記事をシェアする
「ひとり映画」の記事

恋愛映画で知る「世界の日常」 旅に出る前に映画を見よう

映画館にいた猛者は3人のみ「100日間生きたワニ」を観にいった

文化系カップルの青春映画「花束みたいな恋をした」アラフォーのライターがひとりで観たら
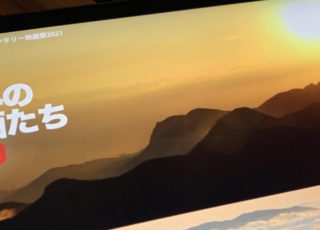
秋の山形で観る「山岳フィルム」 映画館で快適な「山ごもり」

踊りを禁じられた国で踊る男性、公安に追われながら吠えるロック歌手…「世界の多様さ」に目を剥く

社会のルールは「絶対」ですか? 路上生活を知る者たちの「生命のダンス」

『カラブリア』を彩るドキュメンタリー「演出」の力(山形流・映画の作法)

日本一高齢化した街「夕張」の映画を作る伊藤詩織さん「自分が失いかけていたホームを提供してくれた」

ひとり旅で自分だけの「お宝映画」を探せ! 30年目の「山形国際ドキュメンタリー映画祭」