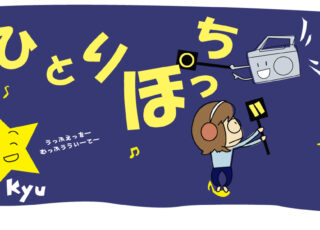同調圧力社会で「ぼっち」になりたい 『ひとり空間の都市論』南後由和さん

「都市でひとりでいるのは正常なこと」。そう語るのは、明治大学情報コミュニケーション学部准教授の南後由和さん。2018年に出版した著書『ひとり空間の都市論』(ちくま新書)で、カプセルホテルやひとりカラオケなどの空間を社会学や建築学の観点から分析しています。さまざまな「ひとり空間」の考察をしてきた南後さんに、その特徴や海外との違いなどについて聞きました。

授業のときでさえ「ぼっち」を意識する学生たち
ーーひとり専用の空間に注目したのはなぜでしょう?
南後:いくつかの理由が重なって、『ひとり空間の都市論』を書くことになりました。ひとつは大学で今の学生を見ていて、キャンパス内でひとりでいることに対し、恥ずかしさや後ろめたさを感じる学生が増えたという印象を持ったからです。
例えば「ぼっち」という言葉が学生の間で揶揄的に使われるようになりました。20年ほど前に僕が学生だった頃は、ひとりで授業を受けることに抵抗感などありませんでした。でも今の学生は、友達とではなく、ひとりで授業を受けていると、「この授業、ぼっち」とSNSでつぶやいたりします。本当に嫌で耐えられないというよりは、自虐的な言葉として使われているんです。

ーーなぜそのように変わったのでしょう?
南後:背景には、メディア環境の変化があると思います。スマートフォンやSNSの普及によって、「常時接続社会」になりました。学生たちは、常に友達同士による緩やかな相互監視の状態におかれています。「レスがないと落ち着かない」「友達がいない人だと思われるのが恥ずかしい」など、常に誰かと繋がっていないと不安だという強迫観念が接続指向をもたらしています。
ただ一方で、それだけ接続指向が強くなるとストレスにもなって、相互監視の状態から逃れたいという願望、つまり切断指向も生まれます。「ひとりの時間」が貴重になり、その「ひとりの時間」が確保された空間が求められるようになるわけです。
ーーすぐに繋がれる時代だからこそ、ひとりになりたいんですね。
南後:最近は学食にも、ひとり向けの席があるんですよ。席の真ん中がパーティションで区切られています。大東文化大学が初期の事例で、今は明治大学にもあります。大学の食堂は、部活やサークルなどのグループが席を占拠することがあるため、ひとりの学生でも居心地がいいように配慮され、空間のレイアウトも変わりました。
ーーそうした学生向けの施設に限らず、日本ではひとり専用の空間が多いと指摘していますね。
南後:日本の都市を見渡すと、ひとり専用の空間が非常に多いんです。ワンルームマンション、カプセルホテル、漫画喫茶、半個室型のラーメン店、最近だとひとりカラオケ店やひとり焼肉店など。世界の主要都市と比べると、「ひとり空間」の種類が圧倒的に多いのが面白いなと思っていました。
社会の変化によって、空間がどう変わるか。あるいは、空間の変化によって、社会がどう変わるか。これまで社会学の立場から、そのような社会と空間の相互作用に関心を持って、都市や建築について研究してきました。「ひとり空間」も、そのような社会と空間の相互作用が、直接的かつ具体的に現れている現象だなと思ったんです。
また、僕自身15年以上東京でひとり暮らしをしていて、自分にとって身近なテーマだったことも、「ひとり空間」についての本を書こうと思った、もうひとつの動機でした。

誰でも「状態としてのひとり」になる
ーー南後さんは「ひとり空間」という言葉を使っていますが、そもそもどう定義しているのでしょう?
南後:何らかの仕切りによって、「状態としてのひとり」が匿名性のもと確保されている空間のことを「ひとり空間」と呼んでいます。何らかの仕切りとは、ひとつは扉や間仕切りなど、目に見える物理的な仕切りのことです。もうひとつは、目に見えない仕切りです。ウォークマンを聞いたり、スマホを利用したりすることで、都市の中で移動しながらでも、目に見えない仕切りによって「ひとり空間」が立ち上がります。
一般的に「おひとりさま」という言葉が使われる場合、未婚の30〜40代を中心とした単身者か、死別による単身高齢者のどちらかを指すことが多いと思います。しかし、夫、妻、子どもがいようが実家で親と暮らしていようが、学校や職場の行き帰りなど、一時的に誰でも「ひとりである状態」を経験しているわけです。そういう「状態としてのひとり」の時間が、どう空間化されているのかに興味がありました。
「ひとり空間」の定義において重要なのは、家族や会社などの帰属集団から一時的に離脱した状態という「時間」の概念とも関係があることです。
ーー「ひとり空間」は移動する途中にあるものだと指摘していますね。
南後:「ひとり空間」のもうひとつの特徴として、「モビリティ(移動性)」との関係があります。社会学者のジョン・アーリは、家と仕事と余暇・社交などの合間にある空間を「中間空間」と呼んでいます。カフェや空港、ショッピングモールなどがそうした空間の例です。
実は「ひとり空間」の多くは「中間空間」に出現しているんです。例えば、駅ナカは、ひとり利用が多い飲食店が集積しています。最近は東京駅などに「STATION WORK(ステーションワーク)」という、15分単位でオフィスワーク利用仕事ができるブースが設置されるようになりました。このような「ひとり空間」も、やはり移動の合間である「中間空間」としてあります。

ーー日本で「ひとり空間」は増えていて、特に東京や大阪などの都市部に多いそうですね。
南後:もともと都市と「ひとり空間」は、歴史的に分かち難い関係にあります。農村や漁村では同質の共同体による暮らしが営まれてきましたが、互いに異質な人びとが多く集まる都市では、プライバシーという概念が重視され、鍵付きの個室が必要とされるようになりました。ホテルが典型例です。近年の日本の都市部では、例えばカラオケや焼肉など、以前は家族や会社の同僚と行くような集団向けコンテンツが個人化し、「ひとり空間」へと変化するようになりました。
ーー南後さんは今年の9月までの2年間、在外研究で海外にいたそうですね。オランダ、ニューヨーク、ロンドンでひとり暮らしをしていたとのことですが、日本と海外では「ひとり空間」はどんな違いがありますか?
南後:日本の「ひとり空間」の特徴は、間仕切りを持った商業空間が多いことです。席を利用するのに1時間いくらなど、課金空間化が徹底しています。
例えばロンドンには、ガーデンやスクエアと呼ばれる小さな公園が多くあります。そこでは、さまざまな数の集団がいる一方で、たくさんの人がひとりでくつろいでいるんですよ。木の下でラップトップで仕事をしていたり、ひとりで寝て日光浴をしていたり。自分たちで居場所を見つけて、「ひとり空間」を作り出しているわけです。しかし、日本の場合は漫画喫茶や間仕切りのあるカフェなど、用意された場所で、しかもお金を払って「ひとり空間」を与えてもらうという違いがあります。
日本では例えば、男性が公園のベンチで座って休憩していただけなのに、不審者扱いされて通報されたというニュースもありましたよね。公共空間において自由に振る舞うことが何かと難しい。これはひとりに限った話ではないですが。
ーー店の看板に「ひとり向け」と書いてあったら入りやすいですよね。何かと周囲の目が気になってしまう。同調圧力の強い社会だからひとりでいづらいんですね。
南後:ロンドンもニューヨークも、実に多種多様な人が住んでいます。人種も宗教も服装も規範意識も、皆がバラバラなので、電車やカフェの中でも他の客のことをあまり意識していない。日本と比べて、周囲の視線を気にするようなことが少なく、ストレスフリーでしたね。

海外でひとりでも食事を楽しめた理由
ーーひとり暮らしのしやすさは日本と海外で違いましたか?
南後:日本のスーパーやコンビニでは、過剰に個別に小さく包装されたパッケージの商品が売られていますよね。「個装文化」と呼んでもいいかもしれません。海外では日本みたいに小さなサイズで売られている商品はなかなかありません。1パックの野菜でも果物でも量が多いんですよ。ひとり暮らしの消費者に向けて、企業側のサービスが行き届いていない。日本みたいにきめ細やかな、「おひとりさま」のお客さま重視の国は珍しいです。
ーーそうすると食事は大変でしたか?
南後:自炊しないという条件つきであれば、むしろ食環境のインフラが整っていて便利でした。というのは「Uber Eats(ウーバーイーツ)」に代表されるデリバリーシステムが発達しているからです。日本ではまだまだファストフードが中心ですが、ニューヨークやロンドンでは、さまざまなカテゴリーのレストランが加盟していて、選択肢が豊富にあります。
「Uber Eats」以外にも、複数の会社が競合していました。例えばニューヨークの「Caviar(キャビア)」というサービスは、ウェブサイトも洗練されていて、「Caviar(キャビア)」限定のローカルなお店が数多く登録されていました。店舗を持たない個人が毎日違うメニューを提供するようなタイプもありました。こういったデリバリーサービスを使っていると、外食に出かける必要性がなくなるですよね。
ーーシェアリングエコノミーが浸透するとひとり暮らしも変わってきそうですね。
南後:この本では、ひとりが都市を移動しながら、住宅外部のさまざまな施設をネットワーク的に使いこなすライフスタイルを「都市的な生活様式」だとし、主なひとり暮らしのあり方として、住宅機能の外部化を念頭に置いていました。しかし、今後は、自動運転などの技術環境の変化によって、あらゆるモノが外部から運ばれてきて、自分の家からまったく移動せずとも、あらゆることが住宅内部で完結するような、ひとり暮らしのあり方も生まれてくるかもしれません。
ーー今後の「ひとり空間」にはどういう点に注目していますか?
南後:ひとりと集団の間の中間スケールの空間に関心があります。例えば、ひとり専用の空間だけじゃなくて、ひとりでも居心地がいいし、集団でも居心地がいい空間ですね。
一括りに「ひとり」と言っても、その中には若者もいれば、高齢者、出張のビジネスマン、外国人、ホームレスなど、実に多様な人びとがいます。都市において、多様なひとりが異質性を保ったまま、いかに共存できるか。今後もそのような問いに、「ひとり空間」がどう姿かたちを変えていくのかに着目しながら向き合っていきたいと思っています。

この記事をシェアする
「ひとり思考」の記事

人生は壮大なドッジボール・ゲーム(AIショートエッセイ 1)

アナログな時代を生きた「古き良き社交場」BARどれすでん

ぼっちとひとり好きは全然違う? 陰キャな女子高生の青春を描く「ぼっち・ざ・ろっく!」
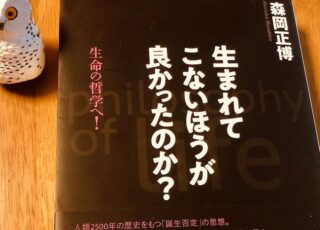
「人は生まれてこないほうがいい?」反出生主義とはなにか〜哲学者・森岡正博さんに聞く

「ひとりには悲しいイメージがある」スペイン人は「ひとり時間」をどうみている?

あなたの街でポツンと咲いてる「野良桜」コロナ禍だからこそ楽しもう

フィンランド人は「ひとり時間」に慣れているので、コロナ禍でもストレスを感じにくい

ズレていたのは「私」だった。圧倒的ぼっちな高校生活を送った男が「大学で学んだこと」

「家でパンツ一丁で酒を飲む」フィンランド人のひとりの楽しみ方