アルコール依存症の連鎖を断ち切りたい 「心の空白」と向き合う写真家・高木佑輔さん

父親がアルコール依存症になってしまったのは、心の「空白」をアルコールで埋めようとしたからーー。そんな写真家の心情を背景にした写真展「SPIN」が11月3日から東京のギャラリーで開かれます。
開催するのは、フリーランスの写真家としてアジア・アフリカを取材するほか、2018年には福島第一原発事故後の世界をテーマにした写真集『Kagerou』が米タイム誌のベスト写真集の一冊に選ばれたこともある高木佑輔さんです。
今回の「アルコール依存症」をテーマにした写真展を準備する過程で、過去の自分と向き合ったという高木さん。父親が毎晩酒を飲んで母親と喧嘩している。そんな環境で育ったために、孤独感や疎外感を抱いていたといいます。

アルコール依存症になってしまった父親のことをどう考えているのか。依存症と「孤独」がどのように関係しているのか。写真展を目前に控えた高木さんに話を聞きました。
酒量の多い父親が怒鳴り、罵声を浴びせていた
――今回の写真展について、聞かせてください。
高木:2年半前に父親がアルコール依存症であることがわかり、なぜこんな風になってしまったのかを振り返りました。酒量の多かった父親が怒鳴ったり、罵声を浴びせていたことを思い出し、自分の奥底に眠っていた孤独感や疎外感が蘇ってきたんですね。同時に、自分も飲み過ぎたときについ、息子に対して感情を爆発させてしまうことがあると気が付きました。
この連鎖は断ち切らなければと思ったんです。結果的にアルコール依存症の父親を題材にした写真展になりましたが、最初は依存症全般のプロジェクトにしようと考えていました。そういうこともあって、同時に制作した写真集では、最後のほうに自分の息子を登場させ、中盤では写真の上に赤いフィルムを置いて、赤ワインで日常が侵食されていく様子を表しました。

「SPIN」という言葉には「回転させる」「紡ぐ」という意味がありますが、父から子へ、子からまたその子へ、と受け継がれる「負のループ」を断ち切りたいという意味が込めています。
――息子さんに対して感情を爆発させてしまうのは、どのようなときなのでしょうか。
高木:飲んでいたり、疲れているときですね。息子は小学校2年生ですが、もう口も立つ年齢です。注意して言い訳されると「バカヤロー」と怒鳴ったりすることもありますね。そのときに「親父と同じことをしてしまっている」と思いますね。
――お父さまは、高木さんが物心ついたころから酒量が多かったとのことでしたね。
高木:そうでしたね。ただ、2年半前にアルコール依存症で病院に搬送されるまでは、自分が依存症だという認識はありませんでした。父は今71歳ですが、どの時点から依存症になったのかはわかりません。入院直前の数年は、ご飯をほとんど食べず、アルコールを飲んではすぐに寝てしまうということを繰り返していました。ところが、家族も「酒癖が悪い」という認識だけで「アルコール依存症」という認識が持てなかったんですね。
結局、病院に搬送されて検査してから、アルコールの多量摂取によって脳が異常に委縮してしまう「アルコール性の認知症」ということがわかったんです。
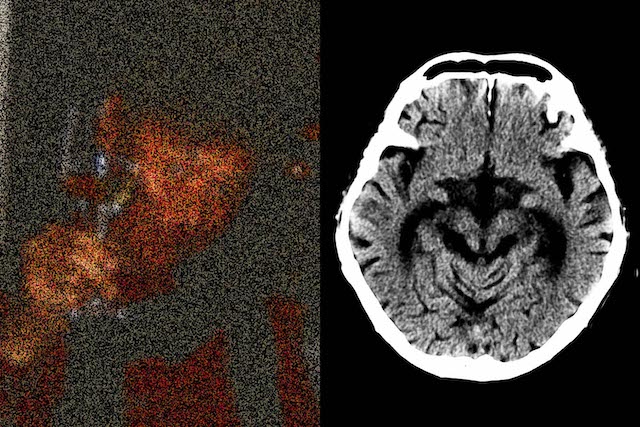
――お父さまとの関係で覚えていることは、どのようなことでしょうか。
高木:平日は仕事で帰宅が夜遅く、休日はゴルフや接待に出掛けていましたが、晩酌時に酒を飲むと母親とずっと喧嘩をしていました。そのことは嫌だったのですが、それが日常の風景で他の世界は知らなかったので、自分の生きている世界はこういうものなんだと受け容れていました。
ただ、中学生ぐらいになって「あれ?うちの家族って変だな」と気付き始めたんです。高校生ぐらいからは漠然と、社会から「isolateされている(孤立させられている)」という感覚がありました。
――そのような疎外感と、のちに写真家になったことは関係あるのでしょうか。
高木:なぜカメラを持つのかといえば、社会を知りたい、自分を知りたいという気持ちがあったからだと思うんですね。明確に自覚していたわけではありませんが、自分は「社会からisolateされている」という感覚がずっとあって、その大元を辿っていくとやはり父親のことがあるのではないかと。

心の空白に「アルコール」というドラゴンが忍び込む
――お父さまの酒量はいつぐらいから増えていったのでしょうか?
高木:元々は商社に勤めていたのですが、当時は酒に対する感覚が甘かった時代ということもあって、酒を飲んで仕事をしていたという話を聞くぐらいに、酒量は多かったんです。その後、50代半ばで不動産業として独立し、家の1階に自分の事務所を構えてからは、家からあまり出なくなりました。そして経営がある程度安定してから、気が緩んできて更に酒量が増えたようです。
それから、9年前に父がかわいがっていた妹が突然、亡くなってしまって…。そのことも影響していると思います。
――孤独と依存症は関係があると思いますか?
高木:密接に関係あると思いますね。人間は、ないものを「ないもの」として楽しんだり、受け容れることができません。その空白の埋め合わせをしようとするんです。
僕にとって、アルコール依存症とは、心の空白にドラゴンが忍び込むというイメージですね。誰もが何かしら心の空白を抱えていますが、そこにアルコールが忍びこむ。アルコールを飲むんじゃなくて、アルコールに呑まれてしまうと。
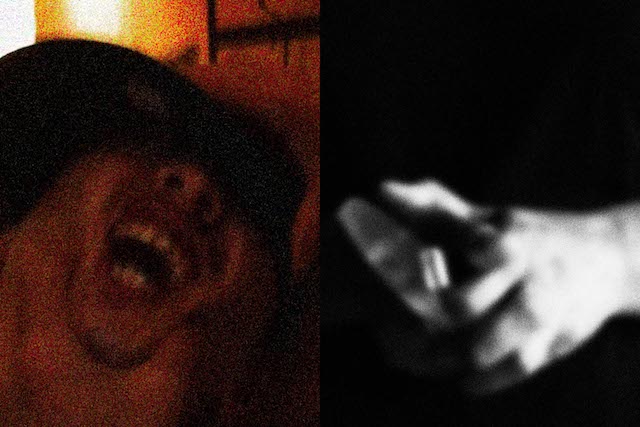
――お父さまは反省していた様子はありますか?
高木:アルコール依存症者にとって一番怖いことは、酒を取り上げられることなんです。入院前も、酒ばかり飲んで体調を崩して病院に行ったことがあったのですが、医師に「アルコールを止めたらどうですか?依存症じゃないですか?」と言われても、「依存症じゃないです、僕はいつでもコントロールできます」と言っていました。反省していないというよりも、アルコール依存症そのものを認めていません。
――お母さまはどうしていますか?
高木:父親は、自宅にいると飲んだことすら忘れてしまうので、再飲酒を避けるために施設にいます。ところが、依存症の自覚がないので、父親は自宅に帰ると言って聞きません。「明日迎えに来い」と父親から母親へ一日に何回も電話があります。
母親には「自分だけが楽しい想いをしている」という罪悪感があるんですね。昔、あれだけ喧嘩していたのに、旅行に行っていたときの楽しい思い出が蘇ってきたようで「喧嘩したけど愛してくれてた」と言っています。都合がいいなぁと(笑)。

誰でもアルコール依存症になる可能性がある
――お父さまがアルコール依存症になって感じていることはありますか。
高木:日本の社会はアルコールに対して寛容と感じます。アルコールで失敗した人に対しても「あれは酒の席だから」とかばいますし、「酒癖が悪い」というのも「普段はちゃんとしているのに」というポジティブなニュアンスにすら受け取れることもあります。
ところが、どこからが依存症なのかわからないのがアルコールなんです。アルコール依存症と言うと、昼間から酒を飲んで路上に寝ている人というイメージがありますが、そうではありません。
アルコール依存症は、脳が快感が覚えて、アルコールにコントロールされている病気なんです。なので、アルコール依存症は、だらしがない人でも、働いていない人でもない、いわゆる普通の人でもなるんですね。

――写真展や写真集を通して伝えたいメッセージは、どのようなことでしょうか。
高木:アルコールは身近なものです。アルコール依存症も同様に、紙一重で誰もがかかってしまうかもしれない恐ろしい病気だ、ということを伝えたいです。アルコール依存症は治りません。しかし、飲まなければ発症は抑えられますので、依存症になったから人生が終わりというわけではありません。
有名人で薬物やアルコールに手を染めた人もいますが、そういう人たちに対するバッシングはすごいですよね。でも、自分や身近な人がいつそうなるのかはわからない。そういう問題として依存症を捉えるきっかけになればいいと思っています。
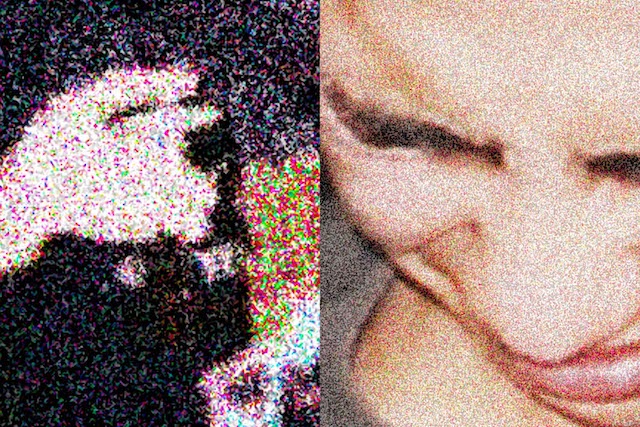
――今後の活動についてお聞かせください。
高木:アルコール依存症の人の家族は他に助けを求めることがなかなかできません。恥ずかしいと感じて周囲の人たちに言えず、家族で抱え込んで孤立して行ってしまうんですね。依存症の人間を抱えた家族同士が助け合う自助グループもあるのですが、自分も最初は存在すら知りませんでした。
アルコール依存症は家族を巻き込む怖い病気で、どんどん家族も疲弊していってしまいます。そういうこともあって、依存症からどのようにして立ち直ればいいのかを考えられるような、回復をサポートできるような活動をしたいと考えています。
――写真展を作っていく中で、自分の気持ちを整理できた部分はありますか。
高木:販売を開始した写真集の編集を昨年からやっていたのですが、製作がカウンセリングになっていました。自分の中での気持ちの整理はできてきました。アルコール依存症の人の家族は離婚したり、縁を切ったりする人もいます。僕自身は、幸せそうな過去の家族写真を振り返ると、その写真をギミックだと感じつつも、これからがんばろう、やっていこうという気持ちになりました。

人間は本質的に孤独な存在
――高木さんにとって、「ひとり」とはどのようなことなのでしょうか。
高木:さきほど話したように、自分はずっと「社会からisolateされている」と思って生きてきました。社会ってそんなもの、人間ってそんなものとくすぶりを抱えていたのですが、父親のアルコール依存症をきっかけとして、依存症とは何かを勉強し始め、トラウマや虐待関連の本もかなり読みました。そして、ヨガも始めました。
そうやって、自分と向き合うことで「孤独であること=自分であること」を認められるようになったんです。やはり人間は本質的には孤独なんじゃないかと。それがありのままの姿なのだと。
そう感じたとき、孤独だと思ってネガティブにフラストレーションを溜めるより、ポジティブに考えて、「ひとりで何かができる」と発想を転換するのがいいと思ったんです。
たとえば、家にいてひとりで本を読んでいるときに、「淋しい」と思うのではなく、好きな音楽を聞きながら本を読んでコーヒーを飲めるなんて「何て幸せなんだろう」と思えばいいわけですよね。自分のありのままを認められるようになると、孤独を楽しめるようになります。意識の持ち方が大切なのではないでしょうか。

◆高木佑輔写真展「SPIN」
期間:2020年11月3日(火・祝)~11月23日(月・祝)
時間:13時~19時
会場:Remainders Photography Stronghold
住所:東京都墨田区東向島2-38-5

この記事をシェアする
「ひとりで作る」の記事

世界を二周して見つけた「私の宝石」 女性起業家がインドでジュエリーブランドを立ち上げたワケ

物語は何かを「納得」するためにある〜時代小説「編み物ざむらい」横山起也さん

「意識が戻るときに見る光の世界を描きたい」アーティストGOMAの紡ぐ世界(後編)

ドクロをモチーフとする唯一無二の陶芸家の挑戦「陶芸をもっとゆるーく楽しんでほしい」

迷作文学がズラリ! ひとりの切り絵画家が生みだす「笑えるブックカバー」が超人気

「時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?」国会議員に聞いてみた理由

「ひとりで全部できちゃうんじゃない?」映像ディレクターが見つけたウェブシネマの可能性

手芸なんかやって、意味あるの? 猟師さんの話から考えてみた

耳の聞こえない監督が撮った災害ドキュメンタリー「聞こえる人に心を閉ざしていた」
















