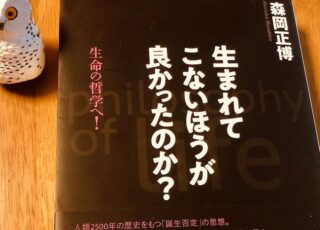「ひたすら音楽を楽しみたい」 ニューヨーク「ジャズ詣で」17年の筋金入りファン

日本では聴くことのできないジャズを聴く。そのためだけに毎年ニューヨークを訪れ、ライブハウスをはしごしているうちに、アメリカのミュージシャンの間でその存在が広く知られるようになった日本人がいます。東京のマーケティング会社に勤める益子博之さん(53)。17年にわたって訪問を続ける益子さんにとって、ニューヨークのジャズの魅力とはいったいなんなのでしょうか。
2002年から続く毎年恒例のニューヨークジャズ詣で
益子さんは学生だった1980年代、仲間とロックバンドを組んでベースギターを弾いていましたが、産業化していくロックにだんだん興味を失っていきました。その一方で、ジャズ研にいたバンド仲間と好きなレコードを交換。マイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンを通じて、ジャズに開眼します。
その後、モダン・ジャズを中心に幅広く聴いていましたが、90年代に入ると、ジャズの新しい曲を聴く機会が少なくなりました。
「日本の雑誌がほとんど紹介しないので、海外の新しいミュージシャンは出てきていないのかと思っていたんです」
ところが、実際は違っていました。世界中から集まって来るミュージシャンによって、ニューヨークのジャズ・シーンは生き生きと脈打っていたのです。ただ、日本のメディアで紹介されていないだけで。
2002年に初めて訪れたニューヨーク。たまたま入った有名ライブハウスで、若手ミュージシャンの新しいジャズの演奏に衝撃を受けました。「日本では聴くことができないジャズを聴きたい!」。翌年から、益子さんの本格的なニューヨークジャズ詣でが始まりました。

ニューヨークに行く日が近づくと、まず、聴きたいミュージシャンやライブハウスのリストを作成します。多いときは3、4カ所、ライブハウスをまわるので、なるべくたくさん聴けるように、移動の経路や時間も入念にチェックして、プランを練りに練ります。
「ただ、ただ、現地で生のジャズを聴きたいだけで。1週間会社を休んで行くんですから、なるべくいっぱい聴きたいんです」
ライブは夜なので、ニューヨークでは昼間は寝ていて、夕方になるとむっくりと起き上がって夜の街に繰り出す。そんなドラキュラのようなスケジュールに徹します。こうして過ごせば、帰国してから時差ボケの影響が少なく、スムーズに仕事に復帰できるというわけです。
ミュージシャンとサポーターが対等なコミュニティ
ニューヨークのライブハウスにやって来るのは、ほとんどが熱心な地元のファンか、ミュージシャンです。また、大半のライブハウスはせいぜい20〜30人規模なので、“よそ者”の益子さんはいやでも目につきます。
広くもないジャズコミュニティのあちこちで目撃されているうちに、益子さんは次第に、ニューヨークのミュージシャンから「自分たちの音楽を聴き、応援してくれる存在」として認知されるようになっていきました。
「いくつかのライブハウスに行くとよく顔を見る常連客が何人もいる。その中にはミュージシャンに慕われている老人が何人かいました。何年か前に、僕も知っている2人が相次いで亡くなったんです。すると、ミュージシャンたちがその死を悼んでイベントをやったりするわけですよ。『サポートしてくれる人たちがいて、その人たちがいるからこそ自分たちの演奏ができる』。そんなふうに、みんな思ってるから。日本のようにスターがいてファンがいて、というのじゃなく、演奏者とサポートする人が対等なんです」
音楽の知識が豊富なうえ、実際にさまざまなミュージシャンの音楽を聴いている益子さんの存在が知れ渡ると、ニューヨークを中心にして、アメリカの音楽関係者の知り合いが増えていきました。

「英語で細かいことまではしゃべれないけど、伝えられる範囲で思ったことを伝えるんです。それが彼らの考えている方向性と合致していたりすると、すごく喜んでくれる」
自分は社交的ではないと、ネットワーキングに関しては受け身ですが、気がつくとフェイスブックには1000人近いミュージシャンの友達が……。その8割が外国人の音楽関係者です。
ジャンルの垣根が崩れつつある
ニューヨークジャズ詣でが始まって17年。この間のニューヨークのジャズシーンは、益子さんの目にはどのように映っているのでしょうか。
「70〜80年代にクロスオーバーとかフュージョン(融合)のブームがありましたが、今はもっと広いジャンルの壁が、どんどんなくなってきています。クラシック、現代音楽、民族音楽……。ニューヨークには世界中から人が集まっているから、その人たちの国の要素も音楽に入ってくる」
女性ミュージシャンとアジア系ミュージシャンの台頭が顕著なのも最近の傾向。ただし、日本人はあまりいないそうです。
「高い評価を受ける女性ミュージシャンが増えています。それから、中国、韓国、インド系の人たちも増えているんですが、おもしろいのは、そういう自分のエスニックなルーツを出す人とまったく出さない人がいること。また、30〜40歳あたりから自分のルーツを掘り始める、みたいなことも見られますね。それぞれ個人的な理由があるんだと思います。ある程度年齢を重ねて、自分は何なのかと見つめ直すようになるんでしょう」
このような傾向は今後さらに強くなっていくと、益子さんは見ています。一方、アニメが好きで日本のゲーム音楽の影響を受けているミュージシャンも多いそうです。さらに、ジャズとヒップホップの融合も目立ちます。
「アメリカでは今、ロックよりもヒップホップのほうが人気がある。ヒップホップのミュージシャンと一緒にやってるジャズマンたちがいて、ジャズがヒップホップの要素を採り入れていたり、その逆もある。ただ、ヒップホップにジャズの記号的なテイストが入っているだけだったりするので、僕にはあまりおもしろくないんですけど。とにかく、ジャズの定義がしにくくなっています。でも、『これはジャズなのかどうなのか』なんて別にどうでもいい」
「本当は音楽について何も言いたくない」
7年前からは3カ月に1度、ニューヨーク音楽シーンの最新情報をジャズファンと分かち合うトークショー「四谷音盤茶会」(次回は10月28日)を東京・四谷で開催しています。「毎回ミュージシャンを招いて、ひとつの音楽に対してこれだけの聴き方がある、というのをぶつけ合うと面白いよね」。音楽雑誌の編集者だった多田雅範氏とそう話し合って始めました。
「僕は音楽業界の人間じゃないので、仕事でやっているわけではありません」。ひたすら音楽を楽しみたい、という益子さんの軸はブレません。
「入り口としての評論とか言葉は、必要だと思うんです。でも、音楽を語るのは難しい。本当は音楽について何も言いたくないんですよ。語れと言われるから語るけど……。言葉にならないものを体験しているというか、言葉にして捉えた瞬間、“それ”になっちゃう。言葉のほうが勝ってしまうから。そうじゃないものが消されてしまって、聴こえてこない。それがもったいないんです。言葉だけを信じずに、それはひとつの捉え方に過ぎないものだということがわかったうえで、聴いて楽しむことができたらいいと思っています」
この記事をシェアする
「ひとり趣味」の記事

ひとり音楽と猫と山下達郎(AIショートノベル 8)

喫茶店から私の「マッチ集め」が始まった(マッチを集める 2)

宇宙人に遭遇したときに歌いたい「この素晴らしき世界」

ひとり時間に「手紙」を書くと、ゆったりした時間が戻ってくる

江戸城の「富士見櫓」をめぐるミステリー。江戸時代のものか、復元か?(ふらり城あるき 11)

なぜ人は「鼻歌」を口ずさむのか? スピッツの「ロビンソン」をきっかけに考えてみた(いつも心にぼっち曲 7)

田んぼの真ん中にバリ風の「ヨガ道場」を建てた女性 なぜこんなものを作ったんですか?

「僕はどれだけ拍手に元気づけられてきたんだろう」コロナ禍で40周年をむかえたスターダスト☆レビュー

SNS疲れで眠れない夜、谷山浩子の「銀河通信」が心を軽くしてくれる(いつも心にぼっち曲)