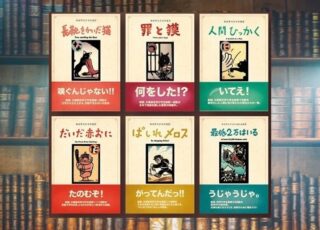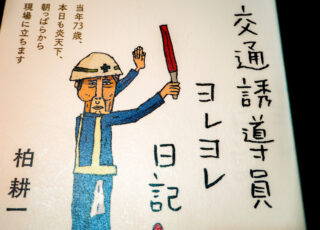演劇が繰り広げられる「レトロ喫茶」 閉店寸前だった店が講じた起死回生の策

カウンター席で熱いコーヒーをすすりつつ、本のページをめくったり、物思いにふけったり。ひとりで喫茶店で過ごす時間は、「孤独である豊かさ」を噛みしめられる有意義なひとときです。
京都にある「フィガロ」もまた、充実の“ひとりタイム”を楽しめる喫茶店。昭和生まれの重厚な内装に感心しつつ、厳選した豆の深いうまみをしみじみと堪能できます。
そして、このフィガロにはもうひとつ、刮目すべき特色があります。それは、喫茶店でありながら「店内で演劇が観られる」こと。この5年のあいだに、さまざまな劇団や表現者たちにより、膨大な数の芝居が店内で上演されてきました。

何も知らずに入った一軒のレトロ喫茶が、実は演劇空間だった。そんなサプライズにあふれたお店は、どういういきさつでできあがったのか。さらに現今の飲食店を悩ませる「新型コロナウイルス」に対する劇的なアイデアとは。店主であり俳優である浦賀わさびさん(40)に、お話をうかがいました。
まるで舞台の大道具 ひとりの時間をしみじみと楽しめる空間
鞍馬や貴船など京都の奥座敷ともいえる地域へとのんびり向かう叡山電鉄。無人の「茶山」駅を降り、線路が軋むカタコト音を背中に聴きながら西へ3分ほど歩くと、喫茶「フィガロ」があります。

2015年9月にオープンした喫茶「フィガロ」。全面ガラス張りのファサードから、柔らかな陽の光が射しこみます。店内は広々としており、壁は堅強なレンガ造り。まるで舞台の大道具であるかのように、ゆったり腰をおろせる大きな椅子はラタン(籐)製。ラグジュアリーな気分にひたれます。

大仰なデザインがなされたヴィンテージ感があるシャンデリアは、おだやかな黄昏色を淡く灯しています。考え事の邪魔をしないソフトな軽音楽がBGM。まろやかな味わいのバターチキンカレーや、ほろ苦い手作りのプリンなど軽食がどれもおいしい。ひとりでくつろぐには、もってこいの止まり木です。


30代で昭和喫茶を受け継いだ舞台俳優
フィガロの前身は1982年(昭和57年)に開店した「アロー」という名の喫茶店でした。現店主の浦賀わさびさんがアローを引き継いだのです。
「明るいママと物静かなマスターの老夫婦が営んでいて、温かな雰囲気でした。とても落ち着くので、よくコーヒーを飲みに来ていたんです。ところが御高齢のため飲食業から引退されると聞きましてね。こんなしっかりした造りのお店、壊したらもう再現できない。それがいたたまれず、買い受けたんです」(浦賀わさびさん)

お気に入りの喫茶店を丸ごと買ってしまうとは、なかなかの度胸。内装やインテリアは、ほぼ往時の姿そのままなのだそう。
「ここまで喫茶店らしい喫茶店って、めったにないでしょう。ご夫婦が、そうとうお金をかけて造られたようです。大きな籐の椅子も昭和のまま。もしも壊れたら、どこに修理に出せばいいのか、修理費はいくらかかるのか、見当もつきません」
30代で昭和遺産的な喫茶店のマスターになるとは。勇気がある、というか、少々無謀にも思える転身です。
「正直に言って本当にやり繰りが大変です。ただ、好きだった店を残したい想いだけではなく、『演劇がやれる場所をつくりたい』という気持ちが強かったんです」
そう、わさびさんはキャリアおよそ9年の舞台俳優。特定の劇団には所属せず、公演ごとのオーディションなどで役を獲得しながら場数を踏んできた一匹狼なのです。

「身体がガリガリですから、よく病床に伏せったり異様に几帳面だったりする人の役などをあてられていました」
店内では5年間で約200本の芝居を上演
個性派俳優であるわさびさんの舞台愛と、得難い昭和喫茶の消滅の危機が、コーヒーにフレッシュミルクが渦巻くように溶けあい、「芝居を披露する喫茶店」として甦ったのでした。オープンした2015年から2020年までのあいだになんと191本もの芝居や舞踊などパフォーマンスが繰り広げられたというから驚き。さらに毎年冬には30日間連続(!)で公演する文化祭も催すのだそう。
「店の名前を考えていた時、たまたま眼の前に自動車のフィガロが停まっていたんです。『フィガロの結婚』という有名な戯曲もありますし、演劇をやるのにぴったりだと感じて店名にしました。そうして、上演したい劇団には店のスペースをどんどん使ってもらっています」

芝居ができる喫茶店の誕生は、演劇界でもたちまち話題となりました。とはいえ「舞台」と呼べるしつらえは、店内のどこにも見当たりません。俳優さんたちは、いったいどこで役を演じているのでしょう。
「俳優がカウンター席に並んで座り、お客さんに背を向けて演じる会話劇とか、ありましたね。演技をしている間、お客さんはずっと俳優ふたりの背中を見ているんです。『あの席のふたり、ヘンな会話してるぞ』『喧嘩を始めたぞ』と、会話を盗み聞きする感覚で。あとはカウンターのなかを使う場合もあるし、どこかのテーブルを使うこともあります。照明を持ち込む劇団もありますが、多くはうちのシャンデリアやランプをそのまま使います。舞台がないので、演出家の腕の見せ所です」

喫茶店のなかで、演じる者と観る者が同じ場所にいる。客電はつきっぱなしだし、喫茶店内の公演だから、観客はドリンクやフードも当然注文できる。いわゆる演劇とはシチュエーションがまるで異なります。
そうして観客たちは単なる入場者ではなく、演劇の設定や装置として機能する。日常と非日常がせめぎあう摩訶不思議な状況に置かれ、一般的なシアターでの観劇よりもスリルを味わえるかもしれません。

芝居を上演していると知らずにやってくるお客さんもいる
なかには、芝居の公演をしているとは知らずに訪れるお客さんもいるのだそう。
「公演中に、コーヒーを飲みにふらーっと入ってくるお客さんもおられます。そっと紙に事情を書いて無言で説明して、それでもいいと、そのまま観劇して入場料を支払って帰られた人もいました。劇団側も上演中にお客さんが入ってくるわけですから、役者のアドリブ力が問われますよね」
芝居の上演は基本的に閉店時間後。とはいえ、営業時間内でも随所に演劇を感じることができます。上演のインフォメーションがファイリングされており、閲覧可能。また、ポテトチップスをはさんだアイルランドに伝わる定番のトーストサンドウイッチ「クリスプサンド」は、同国をテーマにした公演の流れでメニューに登場したのです。このように、いい脇役がそろっています。

「いつかは、公演の告知をせず、普通の喫茶店営業の時間内にいきなり芝居が始まる、みたいなハプニング演出もやってみたいんです」
演劇を鑑賞できるスペースとして息を吹き返したレトロ喫茶。ひとりでふらりと訪れて、もしもそこで芝居が始まったら、一生忘れられない想い出になるでしょう。コーヒーカップから立ちのぼる湯気の向こうに、新しいエンタテインメントの萌芽を見た気がしました。
新型コロナウイルスに対抗する劇的なアイデア
……と、きれいにエンディングを描ければよかったのですが、時局は暗転。人々を苦しめる新型コロナウイルス禍は例外なくフィガロへも襲いかかりました。例年ならば3月から5月のあいだは劇団の上演希望が相次ぐのですが、今年はもっとも早い公演で6月になる予定なのだそう。
「上演の自粛があり、通常の営業時間中も客足が滞りはじめました。先日は遂にお客さんの最低入店記録を塗り替えてしまいました」
このままでは芝居の上演どころか喫茶店の運営自体ができなくなる。なにか手立てはないものか……。頭を痛めるわさびさんの目に、あるものが飛び込んできました。それは11枚綴りの「コーヒーチケット」。
「喫茶店の慣習にのっとり、フィガロも常連さんに向けてコーヒーチケットを販売していたんです。『これを、うちの店へまだ訪れたことがない方にも買っていただけないだろうか』とひらめき、Twitterで呼びかけました」

カンパやクラウドファンディングではなく、「旧来から喫茶店につきもののコーヒーチケットの販売で非常事態を乗り越えよう」。このアイデアがうまくいけば、自分の店のみならず、多くの喫茶店が応用できるはず。この冴えた取り組みに対し、インフルエンサーが反応。ツイートは拡散され、大いに話題となり、ニュース番組にも採りあげられました。まさにスポットライトが当たったのです。

こうして一時的にしのげたものの、危機的状況であることは変わりなく、予断を許しません。しかしながら、未来のお客さんにコーヒーチケットを購入してもらうわさびさんのアイデアは、前売り券というシステムが根づく演劇人だからこそスムースに浮かんだのではないでしょうか。SNSと連動させてゆく見せ方もまた演劇的であると感じました。
いずれにせよこの騒動、一日も早く収束し、千秋楽を迎えてほしいものです。
この記事をシェアする
「ひとりで演じる」の記事

オーストラリアの不思議な民族楽器「デジュリドゥ」に魅せられて〜アーティストGOMAの紡ぐ世界(前編)

40歳、一児の父。「セミプロ」にしか歌えない歌で心を揺さぶりたい

「役者はひとりでやっているとキツイ」俳優が「互助集団」を立ち上げたワケ

「好きなことを続けただけ」米国出身の「不良留学生」が狂言師になった理由

新聞記者を辞めて俳優の道へ「カメ止め」出演の合田純奈さん「死ぬ直前に後悔したくない」

路上でひとり芝居を続ける役者「現実感をもってやれるのはこれしかない」

「ひとりの時間がないと生きていけない」ニューヨークで「RAKUGO」を広める落語家

「他の人と同じようには弾けない」 ピアニスト岡城千歳がひとり多重録音に挑む理由

「ブランドに頼りたくなかった」ヨーロッパ企画を飛び出した山脇唯さん〜ひとりでやる第3回〜