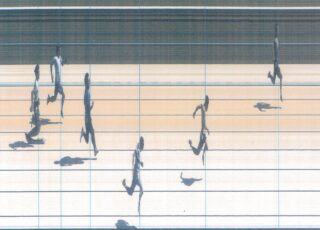耳の聞こえない監督が撮った災害ドキュメンタリー「聞こえる人に心を閉ざしていた」

耳の聞こえない映画監督、今村彩子さんはこの10年間、「災害と耳の聞こえない人たち」をテーマに取材を続けてきました。
東日本大震災(2011)、熊本地震(2016)、西日本豪雨(2018)、そして新型コロナウイルス(2020~)。そんな災害に直面したとき、聞こえない人たちはどのような孤独を感じていたのでしょうか。
これまで見過ごされがちだった人たちの姿を追ったドキュメンタリー映画『きこえなかったあの日』が2月27日、公開・配信されます。
生まれつき耳が聞こえない今村監督は数年前まで、「聞こえる人」に心を閉ざしていたといいます。どんな思いで、この映画を制作したのでしょうか。インタビューしました。
取材のときは手話通訳者に同席してもらい、こちらの言葉を手話で今村監督に伝えてもらいながら、話を聞きました。
震災から10年「聞こえない人」を取り巻く状況は?
――耳の聞こえない人たちと災害をテーマにして、映画を撮り始めたきっかけはなんだったのでしょうか。
東日本大震災が発生したとき、私は名古屋にいました。名古屋では震度3くらいだったんですが、テレビや新聞で「大きなことが起きた」ということを感じました。そのとき、耳が聞こえない人のことが報道されていなかったんです。私自身、生まれつき耳が聞こえないので、東北にいる「耳が聞こえない人たち」はどんな状況におかれているのか、必要なものはなにか、知りたいと思ったんです。
最初は「自分にできることはない」と思っていました。すると「目で聴くテレビ」という、耳の聞こえない人のために手話と字幕で伝えるCS放送局のスタッフから「東北に取材に行けますか?」と連絡があったんです。私は以前、そこでディレクターをやっていたんです。連絡をもらったとき、「あ、私にもできることがある」と思って、震災の発生から約10日後、放送局のスタッフと岩手県宮古市に入りました。
――被災地ではどんなことがわかりましたか?
たとえば、原発事故に関するニュース番組では、枝野官房長官(当時)の隣に手話通訳の人がいるんですけども、最初は画面に一緒に映っていても、枝野さんのアップになると手話通訳が見えなくなってしまう。当時は字幕放送も見られなかったので、耳の聞こえない人は、聞こえる人よりも得られる情報が少なかったんです。
また、「シーベルト」とか「セシウム」といった普段の生活では使わない言葉が出てくる。それらは新聞を読めばわかるんですが、耳の聞こえない人たちのなかには読み書きが苦手な人も少なくないんです。だから不安が大きかったと思います。余震も続いていましたから、夜、ちょっと揺れるとすぐに目が覚めて、かなりのストレスがあったと聞きました。
私自身、東日本大震災の1カ月後に福島に行ったとき、震度6の大きな余震を経験しました。その日は女性スタッフと一緒だったんですが、彼女は昼に名古屋に帰っていったので、夜は私ひとりでホテルに泊まりました。そのときが一番怖かったですね。
もし停電になったら、聞こえないうえに、見えない。世界とのつながりが切れてしまうわけです。これはすごい恐怖です。私は取材が終わったら名古屋に帰れるけれども、被災地の聞こえない人たちは、その恐怖を毎日経験していた。だからこそ、情報の重要性を痛感しました。

ーー「世界とのつながりが切れる」のは、想像するだけで怖いですね。
被災地では、津波の警報が聞こえなくて、そのために亡くなった方もいらっしゃいます。今回の『きこえなかったあの日』で取材させてもらった宮城県の菊地信子さんや加藤褜男(えなお)さんは、近くにいた人に助けてもらって避難できました。ただ、運よく避難所にたどり着けても、そこでの生活で情報が得られないという壁があります。
周りの人に助けを求めようとしても、空気がピリピリしていて、話しかけられないんですね。「みんなも大変なんだから自分も我慢しよう」となる。本当は、そのときに伝えることができれば、周りの人たちも「聞こえない人がいるんだ」と気づける。でも、話しかけなければ、見た目は聞こえる人と変わりがないから、気づいてもらえない。そんななかでいろんな苦労があったと思います。
ーー『きこえなかったあの日』では、東日本大震災からの10年が描かれています。この間、耳の聞こえない人たちを取り巻く状況はどう変わっていますか。
私が取材した範囲では、たとえば新型コロナの際の東京都知事の会見は手話通訳がついていて、ちゃんとテレビに映るようになっていました。会見ではフリップも使うようになったので、簡単な情報は得られる。そういった変化があると思います。手話言語条例(手話の普及・啓発に努めることなどを定めた条例)も全国に広がっていきました。
でも、まだまだだと思います。海外のニュースを観ると、ずっとワイプで手話が映っていて、それを見ればわかるんですね。そうしたものを見ると、日本はまだ過渡期なんだなと思います。
「聞こえる人」は「できる人」に見えて、心を閉ざしていた
ーー監督自身は、この10年でどんな変化があったのでしょうか。
10年も経つと、考え方がだいぶ変わってきました。最初は聞こえる人に対して、どこかで心を閉ざしていたんです。でも、2015年に自転車で日本縦断の旅に出て、いろんな人と出会って、私のなかで大きく変わることができました(この旅はのちにドキュメンタリー映画『Start Line』として公開された)。
『きこえなかったあの日』に出てくる被災者の加藤褜男(えなお)さんとは、その旅の前に会っているんです。加藤さんも耳が聞こえませ。私にもわからない独自の手話を使うし、筆談も難しい。なのに、仮設住宅の周りを散歩して、積極的にいろんなところに顔を出すんですよね。周りの人たちも「かとうさん」じゃなくて「えなおさん」って下の名前で呼ぶ。
加藤さんと住民が親しい関係を築いていることに驚きました。コミュニケーションって、声に出してしゃべるとか、手話で話すとか、筆談をするだけではなかった。加藤さんみたいに手を振ったり笑ったりするだけでも、心を通い合わせることができるんだなとわかりました。

ーー逆に言うと、監督も2015年までは他者とのコミュニケーションが苦手だったということでしょうか。
「聞こえる人、聞こえない人が共に生きる社会を」と映画を撮ってきたのですが、心のどこかでは「聞こえる人」にはわからないという投げやりに近い感情がありました。
だけど、自転車旅を通して、耳の聞こえる人も聞こえない人も、根本的なところでは同じなのかもと感じるようになりました。聞こえる人でもコミュニケーションで悩んでいる人はいっぱいいるんだとわかったんです。すると逆に、「聞こえる人」が身近に感じるようになりました。
それまでは私たちが持っていない「聞こえる」というものを持っているから、どうしても「できる人」に見えてしまうんですね。だから自分のほうで「できる人」「できない人」という区分けをして、自分を守るために心を閉ざしていたんです。だけど、加藤さんにはそれがなかったんですよね。衝撃的な出会いでした。
ーー監督からすると「聞こえる人」はどう見えていたのでしょうか。
コミュニケーションがスムーズにできる。目と目を合わせなくても、スムーズにコミュニケーションができるというイメージがあったんです。みんな楽しく話しているように見えたけど、私はそこに入れなかった。
でも加藤さんは、周りのみんながしゃべっていることがわからなくても、楽しめるんです。私はわからないと楽しめなかったし、何をしゃべっているのか気になってしまう。自分だけ何を言っているのかわからず、さみしくなってしまう。だから、初めから距離を置いていました。
20代のころ、母親がよく「彩ちゃんは怒りで映画を作っている」と言っていました。「なんで聞こえない人のことをわかってくれないんだ」という怒りですね。自分ではあまり意識していなかったですし、自覚もなかったんですけど、母から「怒りが原動力だ」と言われたとき、そうだなと思いました。
「聞こえる人と聞こえない人が共に生きていける社会を作りたい」という方向で作品を作っていましたけど、本当の底の部分にあるのは怒りだったんですね。母はそれがわかっていたんですね。
ーー現在のコロナ禍で、映画業界や映画館がおかれた状況をどう見ていますか。
今までがすごく恵まれていたんだなと思いました。それは新型コロナがなかったら気が付かなかったことでした。コロナ禍が落ち着いてマスクのない生活になったら、人に会うことの喜びをすごく感じられると思います。
映画業界だけではなく全般的に言えるのは、人って何か困難があったとき、どうやったらやっていけるかというのを考えていく力があるんだということです。映画や舞台をネットで配信してみたり、飲食店がテイクアウトとかデリバリーをやってみたり、いろんな工夫で、より良くしたいっていう気持ちを根本的に持っているんだなと。
そういう意味ではみんなが障害者になったと思うんですね。自由に人と会えない、仕事もスムーズにできない。みんなが障害者になって、とても不便な生活を強いられて、もともと障害を持っている人たちの生活に思いを馳せることができるようになった。そういう人たちの生活から逆に学ぶことがあるんじゃないかとか。そうした方向に向かえたらと思います。
(取材後記)
「聞こえない人」への取材は、筆者にとって初めての経験でした。いわゆる不織布マスクでは「口もとの動きが見えない」ということで、TV番組で見る透明のマウスガードを着用しました。
初めは、こちらの言葉が少しでも伝わるようにと、思わず手を動かしながら話したのですが、もしかすると隣にいる手話通訳の「雑音」になるのではと思い直し、できるだけ手を動かさないようにしました。手話通訳がついていても、話者の表情や口の動きが重要だということを初めて知りました。
この記事をシェアする
「ひとりで作る」の記事

世界を二周して見つけた「私の宝石」 女性起業家がインドでジュエリーブランドを立ち上げたワケ

物語は何かを「納得」するためにある〜時代小説「編み物ざむらい」横山起也さん

「意識が戻るときに見る光の世界を描きたい」アーティストGOMAの紡ぐ世界(後編)

ドクロをモチーフとする唯一無二の陶芸家の挑戦「陶芸をもっとゆるーく楽しんでほしい」

迷作文学がズラリ! ひとりの切り絵画家が生みだす「笑えるブックカバー」が超人気

「時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?」国会議員に聞いてみた理由

「ひとりで全部できちゃうんじゃない?」映像ディレクターが見つけたウェブシネマの可能性

手芸なんかやって、意味あるの? 猟師さんの話から考えてみた

タイムラプスは「四次元の旅」 運とカンが頼りのワクワク感がたまらない