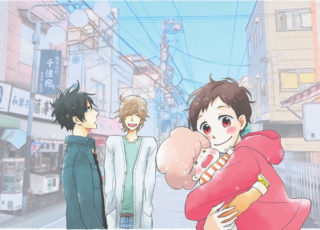モンゴル遊牧民と日本人、共通点は? 世界の辺境を旅する写真家が語る

「過酷な環境のなかでも、人はしたたかに生きている。すごく優しくて、すごく強い」。そう語るのは、チベット文化圏を中心に世界中を旅しながら撮影する広島県在住の写真家・松尾純さん。モンゴル西端の遊牧民の暮らしをカメラにおさめました。
遊牧民の「過酷な移動」を撮影
東京・銀座のニコンサロンで開かれた個展『クゼゥゲ・クシュ Kuzeuge-Kushu』(6月26日まで開催)では、モンゴルの首都ウランバートルから西へ1600キロ離れたバヤン・ウルギー県で撮影された写真が展示されていました。

展覧会名になった「クゼゥゲ・クシュ」とは、現地に住む遊牧民・カザフ族の「春の移動」のこと。彼らは家畜が食べる新しい牧草を求めて、年4回の大移動をします。そのうちでも、もっとも過酷だといいます。松尾さんは昨年2月から3月にかけて、彼らと行動をともにしました。
「春に向けた移動のことで、実際は冬なんです。まだ気温も低く、家畜も食べ物が少ないからやせ細っている。そんな厳しい環境のなかでも、たくましく生きている人々の姿を撮りたいと思いました」(松尾さん)

大型の鳥・イヌワシを使って狩猟をする「鷹匠(たかしょう)」の姿も展示されています。
「耳の不自由な鷹匠・カザルベックさんを撮影しました。彼はとても無邪気でドジを踏む人なんだけれど、イヌワシを持つとすごくたくましく見える。鷹匠の仕事をして歌を歌ったり楽器を演奏したりする。そんな生活を本当に幸せそうに生きています」

人間の営みは共通している
松尾さんは風景だけでなく、人を撮影することにこだわっています。
「どんなに遠景の風景でも、人が入っています。こんなにだだっ広い、厳しいところなのに、人が生きている。過酷な環境のなかで、したたかに生きている。すごく優しくて、すごく強い。そこに感動するんですよ」

松尾さんがモンゴルに惹かれるのは、そこに日本とは全く違う環境があるからだといいます。文化の違いを感じた会話をこう振り返ります。
「あるおじいちゃんが、私に『君はどんな家畜を飼ってるの?』と聞くんです。『日本では家畜を飼うのは一部の人だけ』だと答えると、次は『草はいつ生えてくるんだい?』と聞かれる。家畜や草のことをいつも気にしているのが、当たり前なんです」

しかし、人間の営みには、モンゴルでも日本でもで共通する点があるといいます。それは、「助け合って生きていること」だと松尾さん。
「モンゴルの人々の暮らしには周りの人の支えがあります。鷹匠の生活は、仕事をしているときは、奥さんが家の仕事を全部担っている。孤高のハンターじゃなくて、みんなの協力があってできている仕事なんです」
そのような「助け合い」は、松尾さんも同じなのだと話していました。

「私自身、家族や周りの協力が無くしては、撮影ができなかったと思っています。日本でも、最近は震災のボランティアに参加するような若い人も増えている。遠い話ではない。より身近に感じてもらえるのでは、と思います」
この記事をシェアする
「ひとり仕事」の記事
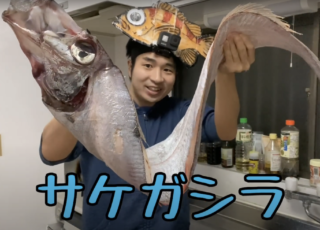
「10歳のころの自分が笑えるネタか」さかな芸人ハットリさんが大切にしていること

「目撃すれば幸せになれる」とウワサが広がる「自転車で文字を売る男」

個室のない私が「畳半分のワークスペース」を手に入れるまで

ひとりで山を歩き「食べられる野草」を探す 「山野草ガイド」を作る地域おこし協力隊員

「当たればお立ち台、はずれたら死刑台」競馬場で「予想」を売る伝統芸

おじいさんたちに混じり「大工見習い」として働く31歳女性「毎日幸せだと思って生きている」

「どう乗り越えてやろうかワクワクした」危機を楽しむ強さでコロナに打ち勝つ

大学を中退したのは「回転鮨」が原因だった 「出張鮨職人」のイレギュラー人生

「出張鮨」を誰でも楽しめるものに 「スピード命」の型破りな鮨職人